「クラウドコンピューティング」って聞くと、なんだかフワッとしてつかみどころがない…
そんな印象を持っていたのは、きっと私だけじゃないはずです。
私も、基本情報技術者試験の勉強中に“クラウド”が出てくるたびに、「あんまり出題されませんように…」と心の中でそっと祈っていました。(※結果、奇跡的に出ませんでした。ホッ)
ですが現実のIT現場では、クラウドの存在感はどんどん大きくなっています。
「このシステム、将来的にはクラウド対応も視野に入れていて…」という話を何度も耳にするうちに、逃げてはいられないなと本気で思うようになりました。
この記事では、かつて“クラウドアレルギー”だった私が、初心者の目線から「クラウドってつまり何なの?」をイチから丁寧に解説していきます!
そもそもクラウドってなに?雲の正体を暴く
「クラウド」という言葉、なんとなくITっぽくてオシャレな響きがありますが、「何がどうクラウドなのか?」と聞かれると、うまく答えられない人も多いのではないでしょうか。
私もそうでした。というか今でも「雲ってなんなん?」って思っています(笑)。
クラウド=インターネット越しの貸し借りシステム?
クラウドとはざっくり言えば、「自分のパソコンに入っていないものを、インターネットを通じてどこかの誰か(=クラウド提供者)のリソースを借りて使う仕組み」です。
昔は、Wordのデータも、写真も、アプリも、全部パソコンに保存して使っていました。
でも今は、GoogleドライブやiCloudに保存しておけば、スマホでもタブレットでも見れるし、パソコンを買い替えても困らない。
これがまさに“クラウドで生きる”ってことなんです。
なぜ「クラウド(雲)」って呼ばれてるの?
クラウドという言葉は、昔からネットワーク図で「インターネット」を“雲のマーク”で表すことが多かったことに由来しています。
雲の向こう側で何が起きているのかは見えないけど、ちゃんと繋がっていて、必要なものが使える
――そんな意味合いですね。
オンプレミス vs クラウド:どっちがどう違う?
ここでよく出てくる言葉が「オンプレミス」。
これは自社でサーバーを買って、メンテして、全部自分で管理する昔ながらのスタイルです。
一方、クラウドは「必要な分だけ借りるレンタル型」。
例えるなら:
| スタイル | イメージ | 管理の手間 | 初期コスト |
|---|---|---|---|
| オンプレミス | 自宅を建てる | 多い | 高い |
| クラウド | 賃貸物件 or ホテルに住む | 少なめ | 安め |
自宅(オンプレ)は安心だけど大変。ホテル(クラウド)はお金払えば誰かが掃除もセキュリティもやってくれる感じです。
なぜ今クラウドなの?時代の波に乗る理由
ITの世界ではトレンドの移り変わりが早いですが、「クラウド」はもはや“流行”を超えた“インフラの常識”になりつつあります。
では、なぜここまでクラウドが広まったのでしょうか?3つの理由に分けて、初心者目線で見ていきましょう。
理由その1:初期費用がグッと抑えられる
従来のオンプレミスでは、サーバー機器を買ったり、設置スペースを確保したり、なんなら冷却設備まで必要だったり…
まるで「ITの家を建てる」ような感覚でした。
それに比べてクラウドは、必要な分だけ月額料金で利用できる“サブスク型”のITインフラ。
つまり、IT投資のハードルがグッと下がって、小さな会社や個人でもスタートしやすくなったんです。
理由その2:急なアクセス増にもスイスイ対応できる
たとえばブログが急にバズってアクセスが爆増したとしても、オンプレミスならサーバーが落ちて「あわわ…」と青ざめることに。
でもクラウドなら、自動的にリソースを増減してくれる“スケーラビリティ”のおかげで、柔軟に対応してくれます。
これは本当に便利。まるで「混んできたら勝手に席を増やしてくれるレストラン」みたいな感覚です。
理由その3:どこでも仕事ができる!リモート時代の味方
コロナ禍以降、リモートワークが一気に普及しました。
それに伴ってクラウドの価値も一気に加速。
なぜなら、クラウドを使えば、家でもカフェでも温泉旅館でも(!?)仕事ができるから。
必要なデータがすべてインターネット上にあるので、いちいちUSBにコピーして…なんて手間は不要。
「あ、あのファイル家のパソコンにしかない!」という昔のあるあるも、クラウド時代には解消されます。
クラウドの3兄弟?IaaS・PaaS・SaaSの違いを理解しよう
クラウドの説明を読むと、必ず出てくる「IaaS」「PaaS」「SaaS」。
初見だと「アイアース…?サース…?誰…?」と呪文のように聞こえがちです。
でも、これはそれぞれ“クラウドのどの部分を提供してくれるか”の違いに過ぎません。
ざっくり言うとこうです:
- IaaS(イァース):インフラを提供(サーバーやネットワークなどの基盤)
- PaaS(パース):開発環境を提供(アプリを作るための土台)
- SaaS(サース):完成済みのソフトウェアを提供(すぐ使えるサービス)
これをわかりやすくするために、「ピザを食べたいときの選択肢」で例えてみましょう。
ピザ理論で覚えるIaaS・PaaS・SaaS
| モデル | 何をする? | ピザにたとえると… |
|---|---|---|
| IaaS | 材料とオーブンは貸すけど、作るのは自分でがんばってね | 生地や材料をもらって、自宅のキッチンで焼く |
| PaaS | キッチンも材料も道具も用意済み。焼くだけ | お店の厨房を借りて、トッピングして焼くだけ |
| SaaS | もう焼けたピザを持ってきてくれる。食べるだけ! | Uber Eatsで届いた熱々ピザを食べるだけ |
それぞれの立ち位置をざっくりつかんでおくだけで、クラウドの使い道がグンと理解しやすくなります。
具体例もあわせておさえておこう
| モデル | 有名なサービス |
|---|---|
| IaaS | AWS EC2、Microsoft Azure VM、Google Compute Engine |
| PaaS | Heroku、Azure App Service、Google App Engine |
| SaaS | Gmail、Dropbox、Slack、Notion、Google Docs |
クラウドってどう使われてるの?現場でのリアルな活用事例
「クラウドって便利らしいけど、実際のところどんなふうに使われてるの?」
そんな疑問を持つ方も多いはずです。
ここでは、企業でも個人でも活用されているクラウドのリアルな使い方をいくつかご紹介します。
① データの保存と共有:USBの出番、激減中
昔はファイルをUSBに入れて、会社に持って行ったり、友だちに渡したり…という時代でした。
でも今は、Google ドライブやDropboxなどのクラウドストレージを使えば、どこからでもファイルにアクセスできるし、共有も一瞬。
たとえば、チームメンバーと同じ表計算ファイルをリアルタイムで編集したり、写真をまとめて共有したり。
「持ち運ばない便利さ」が、クラウドの一番の恩恵かもしれません。
② ソフトウェアもオンラインで:SaaSの世界へようこそ
メール(Gmail)、文章作成(Google ドキュメント)、デザイン(Canva)、プロジェクト管理(Notion、Trello)
… 今や多くの作業がインストール不要で、ブラウザからすぐ使えるSaaS(Software as a Service)で完結します。
「え、もしかして毎日SaaS使ってた?」と気づいた人、あなたはもうクラウドユーザーです!
③ クラウド開発環境:ローカル卒業のススメ
クラウド上で開発できる環境も増えていて、GitHub CodespacesやReplitのようにブラウザ上でコーディング&ビルドが完結するツールが人気です。
「PCの環境構築で3日終わった…」なんてこともなくなり、開発スピードも爆上がり。
また、複数人でコードを共同編集したり、Pull Requestのレビューもサクサク進められるようになります。
④ システム運用にも:企業もクラウドに乗り換え中
業務システムやECサイト、社内の勤怠・顧客管理ツールなども、従来のオンプレミス型からクラウドへ移行している企業が増えています。
実際に私が関わった案件でも、「今はオンプレだけど、次の更新ではAWSに乗せ替えようか」という話題が出ることがよくあります。
導入には多少のハードルもありますが、「運用の効率化」「柔軟性の向上」「BCP(事業継続計画)対応」にメリットがあるため、移行を本格的に検討するケースも増えているようです。
落とし穴もある?クラウドのデメリットと注意点
ここまで「クラウド、便利すぎる!」とテンション高めに紹介してきましたが、ちょっと待った。
どんな便利な道具も、使い方を間違えたり、仕組みを理解せずに使ってしまうと、思わぬトラブルにつながることがあります。
クラウドにも、いくつか“気をつけたいポイント”があるんです。
① ネットがなければただの雲
クラウドの最大の前提は、「インターネット接続があること」です。
どんなに高機能なクラウドサービスも、通信が不安定だったり、圏外だったりすれば、まったく使い物になりません。
たとえば、移動中にGoogle ドキュメントが開かず「…あ、電車の中で資料直そうと思ってたのに…」と膝から崩れ落ちる、なんてことも。
とはいえ、最近はオフラインでも一時的に作業できる工夫もされているので、心配しすぎなくても大丈夫。
「ネットが空気レベルのインフラである」ことが前提なんですね。
② セキュリティの“お任せ”しすぎに要注意
クラウドサービスの多くは、高度なセキュリティ対策を施していますが、それでも「完全に任せきり」にはできません。
- パスワードの使い回し
- 公衆Wi-Fiでのアクセス
- 共有リンクの取り扱い不注意
…など、ユーザー側の使い方次第で、情報漏えいリスクが増えてしまうんです。
クラウドは“鍵付きロッカー”ではありますが、鍵を首からぶら下げて歩いていたら意味がありません。
最低限のセキュリティ意識は持ちつつ、便利に使いたいですね。
③ 月額課金のワナ?気づいたら課金地獄
クラウドサービスの多くは月額制や従量課金制。
「最初は無料枠で十分だったのに、いつの間にかストレージが足りなくなって課金…」「試しに登録したサービスが、気づいたら毎月引き落とされてた」なんてことも。
特に開発系のクラウドサービスは「従量課金(使った分だけ課金)」のものが多いので、「テスト環境を立てたまま忘れてた…」で、請求書に冷や汗をかくケースも。
便利さの裏にある「料金設計」は、しっかり確認しておくことが大切です。
まずはここから!クラウドと仲良くなるためのステップ
クラウドがなんとなく身近に感じられてきた…とはいえ、「いざ使うとなると、どこから始めればいいの?」と迷ってしまう人も多いはず。
大丈夫、最初は誰だって“ふわふわクラウド迷子”です。私もそうでした。
ここでは、私自身が「これは取り組みやすかった!」と感じたクラウド入門ステップをご紹介します。
Step 1:日常生活の“クラウド化”から始めてみる
まずは肩肘張らず、普段の生活にクラウドを取り入れてみることからスタートするのがおすすめです。
- Google ドライブでファイル整理してみる
- スマホの写真をiCloudやOneDriveに自動保存する
- Notionでメモ帳代わりに使ってみる
こういうちょっとしたところから始めると、「あ、クラウドってこういう感じか〜」と実感がわいてきます。
Step 2:クラウドサービスの“無料枠”を活用する
いきなり契約するのはちょっと不安…という方には、各クラウドサービスが提供している「無料枠」を試すのが一番!
- Google Cloud Platform:90日間無料のクレジット
- AWS(Amazon Web Services):12か月間の無料利用枠あり
- Microsoft Azure:無料アカウント&開発者向け特典
これらは初心者が「どんなことができるのか」を体感するのにうってつけです。
無料とはいえ油断して放置していると課金される場合もあるので、使用量の確認はお忘れなく!
Step 3:興味のあるジャンルで“使ってみる”を優先しよう
クラウドは“使ってナンボ”です。座学で学び続けるよりも、ブログをクラウド上で管理してみる、ポートフォリオをGitHub Pagesで公開してみるなど、「自分の目的」と結びつけるのが上達の近道。
私の場合は、「毎朝9時にブログを公開する」ための仕組み作りを、クラウドと自動化(GitHub Actions)で実現してみたり。
正直、最初はつまずきの連続でしたが、「あ、動いた!すご!」の感動がクセになりました。
Step 4:わからなくてもOK!ググれば仲間がいる
クラウドは奥が深いぶん、わからないことがあって当たり前。
でも安心してください。クラウドに関する情報は、QiitaやZenn、公式ドキュメント、YouTube、ブログなどにたくさん転がっています。
そして何より、「私も分からなかった!」と語る仲間が大勢います。
クラウドは、魔法のツールではありません。
でも、うまく使えば私たちの生活や仕事をぐんと柔軟に、快適にしてくれるパートナーです。
まずは小さく始めて、ちょっとずつ仲良くなっていきましょう!

「クラウド」という、ちょっとフワッとしてとっつきにくい存在を、少しでも身近に感じてもらえたなら嬉しいです。
私自身、最初はクラウドが苦手で、「試験に出ませんように…!」と祈っていたタイプでした。でも現場に出て、その存在感に日々圧倒されるうちに、「やっぱりちゃんと向き合いたい」と思うようになりました。
この記事はそんな私の再出発の記録でもあります。 もし、あなたが「今さら聞けない…」と感じていたなら、それは私も全く同じでした。だからこそ、これから一緒に、少しずつ、クラウドと仲良くなっていけたらと思っています。


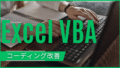
コメント