エンジニアとしていろいろな業務をこなしてきたけれど、ふと立ち止まって考えることがあります。
「……で、私の“得意”って何?」
フロントもちょっとできる。バックエンドもたまに触る。
社内のツール整備も任されるし、なぜか議事録まで丁寧だねって褒められる。
そう、私は“なんでも屋さん”タイプのエンジニアです。
でもある日、ふと思いました。
「このまま便利なだけの存在でいいのかな?」って。
特化型で深いスキルを持っている人を見ると、「これぞプロ…!」と憧れる反面、自分は“何かを極めたわけではない”という引け目も感じてしまう。
とはいえ、強みって「目に見えるすごさ」だけじゃない気もして——正直モヤモヤが拭えませんでした。
この記事は、そんな私と同じように「得意がないかも」「方向性が見えない」と感じている方に向けて、自分のキャリアを再確認するヒントをまとめたものです。
“得意がない”と思っているあなたも、きっとまだ気づいていないだけで、立派な“らしさ”を持っています。
私の試行錯誤も交えながら、一緒にキャリアの道を見直してみませんか。
“得意がない”と感じるのは、自分だけ?
エンジニアとしてある程度の経験を積んできたはずなのに、ふと立ち止まってしまう瞬間があります。
「これといって得意って言えるものがない」
「自分より専門性が高い人はいくらでもいる」
「気づけば、いつも“そこそこ”で止まっている気がする」
私自身も、まさにこの気持ちに悩んだことがあります。
業務上は必要とされているけれど、「自分じゃなくてもいいのでは?」と感じてしまうあの感覚。
得意がない=価値がない、と結びつけてしまうと、途端にキャリアの行き先が不安になりますよね。
中級エンジニアが感じやすい“キャリアの中だるみ”
このモヤモヤは、スキルアップへの意欲がなくなったわけではありません。
むしろ努力してきたからこそ、「なのに、なぜ今ここで迷っているんだろう」と戸惑ってしまうのです。
- 初級の頃は、学ぶことすべてが成長につながる
- でも中級に入ると、全体の流れがなんとなく分かり、課題も“こなせてしまう”ようになる
- ただ、こなしているだけでは「得意」や「強み」には見えにくい
そう、この段階では“技術的な習熟”と“キャリアの方向性”のあいだにズレが生まれやすいのです。
比較の罠にハマっていませんか?
特に社内やSNSで「〇〇のエキスパート」と名乗っている人を見ると、自分との距離感に落ち込んでしまうこともあります。
でも忘れないでほしいのは、誰もが最初から“強み”を確立していたわけではないということ。
むしろ、「得意がない」と感じる時期があったからこそ、自分の方向性を見つけていった人がほとんどです。
だからこそ、「何者にもなれていない」と感じる自分に不安にならなくて大丈夫。
“得意”は、探すものではなく、築いていくものなのです。
次章では、「なんでも屋さんであること」の価値や、中級エンジニアにありがちな“器用貧乏感”の正体を深掘りしていきます。
それがキャリアの足かせになるどころか、実はこれからの武器にもなりうるかもしれませんよ。
“なんでもそこそこ”の正体:中級者のあるある症状
「一通りはできるけれど、特別うまいわけじゃない」
「〇〇さんみたいに何かに突出してる感じがしない」
「自分は器用だけど、専門性って言えるほどじゃないかも」
こんなふうに、自分を“なんでも屋”だと感じている中級エンジニアの方も多いのではないでしょうか。
私もかつて、そう思っていました。
インフラも触った。フロントもやってる。
業務効率化もドキュメント整備も、割とそつなくこなしてきた。
でも、どれも“極めた感”がない。だからこそ、「これが自分の強みです」と胸を張って言えない。
実はこれ、“中級者あるある”なんです
一見ネガティブに捉えがちな「なんでも屋感」は、成長の証でもあります。
なぜなら、初心者の頃は1つの技術に集中するしかなく、複数の領域に手を出す余裕はありません。
中級になってようやく“なんでもやれる”状態になったからこそ、 「自分には特化した何かが足りない」と感じるようになるのです。
これは、視野が広がったからこそ見えてくる課題とも言えるでしょう。
比較すると「自分が薄く見える」現象
SNSや社内の周囲と比較して落ち込むのも、よくあることです。
「〇〇さんはRustに強い」
「△△さんはチームファシリテーションがすごい」
そういう“光る肩書き”を見かけるたびに、「それに比べて自分は…」と焦ってしまう。
でも実際には、尖ったスキルがない=ダメ、ではありません。
その人たちも、“あれ以外は苦手”かもしれないのです。
むしろ、複数の分野に対応できるバランス感覚や柔軟性は、チームの中で非常に貴重なスキルです。
ただ、それが“強みとして認識されにくい”だけ。だからこそ、評価されづらい・実感しにくいのです。
「特別な得意」がなくても大丈夫
強みとは、「キラーワード」や「明確な専門性」だけではありません。
それよりも大事なのは、「価値があるスキルを自分自身が気づいているかどうか」です。
たとえば:
- チームでの調整役として場を整えている
- 小さな不具合や運用ミスに気づきやすい
- わかりづらい仕様を他のメンバーにかみ砕いて説明している
こうした力は見えにくくても、現場ではとても重宝されるものです。
自分では“特別ではない”と思っているスキルが、他の人から見れば“得意”なのかもしれません。
「なんでもできるけど、得意がない」 そう感じているあなたも、実は“できていること”がたくさんあるのです。
次章では、そんな“すでに持っている力”に目を向け、自分の中にある得意や武器の種を言語化・可視化していく視点をご紹介します。
“得意を作る”のではなく“可視化する”という選択
「何かに特化しなきゃ」「強みを作らなきゃ」 そう思うほど、なにを極めればいいのかわからなくなってしまう。
でも実は、“新たな得意を生み出す”ことよりも、すでにあるスキルや経験を整理して「可視化する」ことのほうがずっと現実的で、そして効果的だったりします。
自分では“特別”と思っていないことが、他人にとっては立派な価値
私たちは、自分の中では「できて当たり前」だと思っていることを、あえて「得意」とは言いません。
でも、たとえば次のようなこと、思い当たりませんか?
- 急な仕様変更にも冷静に対応できる
- 誰よりも業務知識があり、チームに伝えられる
- 複雑な処理を図解にして説明できる
- プロジェクトメンバーの作業を整理・サポートしている
どれも派手さはないけれど、「いると安心される」存在って、実はすごく大きな価値です。
“できているのに見えていない”問題を解消する
振り返ってみれば「なんでも屋」のようにいろいろな業務をしてきた中に、ちゃんと成果が積み上がってきているはずです。
でもそれって、「○○の実績」として明示しない限り、自分でも気づきにくいし、他人にも伝わりません。
だからこそ必要なのが、“自分のやってきたこと”を見える化する=棚卸しする習慣です。
小さなアウトプットが「らしさ」を教えてくれる
ここで役立つのが、小さなアウトプット。
たとえば:
- ブログでちょっとした技術的工夫をメモしてみる
- Qiitaに「これ、最初つまずいたけど解決できた」記事を書く
- チーム内にTipsや改善提案をドキュメント化する
こうしたアウトプットを重ねるうちに、「自分はこういう視点が強みなんだな」「こういう説明が得意かも」と、自然と“らしさ”が見えてくることがあります。
得意とは、机に向かってひねり出すものではなく、行動の中から見つかるものなんだと思います。
これまで「得意がない」と思っていた人も、きっと“得意の原石”をたくさん持っています。
あとは、それに名前をつけて、少し外に出してみるだけ。
次の章では、その見えてきた“強みの種”をどう育て、キャリアとして整えていくかについて、具体的なステップをご紹介していきます。
得意がない自分でもできる、キャリアの整え方3選
「自分に得意なんてないかも」と思っていた私が、いま少しずつ“らしさ”を言語化できるようになってきたのは、小さな行動の積み重ねがあったからです。
「得意を見つけなきゃ!」と焦るよりも、「日々の中にある強みのヒントを拾い集めていく」感覚が近いかもしれません。
ここでは、そんな私の実体験や周囲の声をもとに、特別な準備がなくても今日から始められるキャリア整え術を3つご紹介します。
① 日々の業務を記録する習慣
まず最初におすすめしたいのは、“できたこと”を定期的に書き出す習慣です。
とくに中級エンジニアになると、日々の業務が「当たり前」になってしまい、自分が何をしてきたか意外と忘れてしまいます。
- 今日対応した問い合わせの中で、誰かを助けたことは?
- 自然にやっていた“地味だけど重要なこと”って?
- 「ありがとう」と言われた場面はあった?
最初は箇条書きでもOK。Notionやメモ帳でも構いません。
積み重ねていくと、「自分がどういう行動で価値を出せていたか」が見えてきます。
② 小さくアウトプットする
強みを見つけるには、“書く”ことがとても有効です。
完璧な知識でなくてもいい。
失敗談でも構いません。
自分の言葉で「やったこと」「考えたこと」「気づいたこと」を発信してみると、不思議と自分の得意が浮き彫りになってきます。
たとえば…
- 社内WikiにTipsを書いてみる
- 技術ブログに“つまずきポイント”をメモしてみる
- SNSに業務の小ネタを投稿してみる
「説明がうまい」「まとめ方がわかりやすい」「目の付け所がいい」
——そんなフィードバックから、自分では意識していなかった得意に気づくこともあります。
③ 今の自分を棚卸しし、次の小さな学びへ
自分のスキルを棚卸しすると、「あ、意外といろんなことやってきたんだな」と再発見があります。
その上で、「ちょっと伸ばしてみたい」「気になっていたけど後回しにしていた」スキルや分野を選んで、次の一歩につなげていくのです。
- 興味はあるけど自信がなかった領域に軽く手をつけてみる
- 資格勉強を“学びの入り口”として活用する
- 小さな技術検証を個人でやってみる
「得意を見つけること」より、「どこに向かって自分を整えていくか」を意識するだけで、キャリアはぐっと前進します。
得意とは、“いまの自分を認めること”と、“これからの自分を育てていくこと”の間にあると思っています。
次章では、いま感じている「得意がない」という悩みが、じつは誰もが通る成長の過程であり、だからこそ抜け出せるということをお伝えしていきます。
焦らず、自分のペースで、キャリアの道を一歩ずつ整えていきましょう。
“中級の壁”は誰でも通る。だから抜け出せる
「得意がない」「自信がない」「何者でもない」 そんな風に感じてしまうとき、人はつい立ち止まりたくなってしまいます。
でも——それって、実は次に進もうとしている証拠なのかもしれません。
モヤモヤは“キャリア停滞”ではなく“成長痛”
中級の壁とよばれるこの時期は、言ってみれば「今までの自分のやり方だけでは進めなくなったタイミング」。
こなす力はついた。
けれど、「これから何を深めればいいのか」が分からなくなってしまう。
それは、無力なのではなく「成長に飢えている」状態とも言えます。
むしろ、このモヤモヤを経験しないまま器用にキャリアをこなしてしまう方が、長期的には危ういのかもしれません。
強みとは、“旗”ではなく“積み重ね”
「これが自分の強みです!」と堂々と語る人を見ると、うらやましく感じるかもしれません。
けれど、その強みも、ある日突然降ってきたわけではなく——
- たくさんの失敗の中から気づいた小さな得意
- 周囲に求められることを続けたら育ってきた分野
- 自分では気づかなかったけど「それ得意だよね」と言われて意識したもの
こうした地味な積み重ねの結果、“強み”と呼ばれるようになっただけです。
だから、今の自分にまだ「旗」が立っていなくても大丈夫。
あなたが今、淡々と向き合っていることが、やがて振り返ったとき“らしさ”として浮かび上がってくるはずです。
キャリアは“特別感”よりも“つながり”でできていく
特定の専門分野にこだわらなくても、自分なりのつながりや視点をもって言語化していくことこそ、中級エンジニアが次のステップに進む鍵になります。
- なんでも屋としての対応力 × 課題整理力
- 決まった技術ではなく、相手の理解度に合わせた説明力
- スキル横断の経験を活かした「つなぐ力」
こうした“複雑で多様な現場”を支える力がある人は、変化の激しいエンジニアキャリアの中で強く求められていきます。
まとめ:あなたの強みは、これからできていく
「得意がない」と感じることは、決して悪いことではありません。
むしろ、それを見つけようとしている時点で、あなたはすでにキャリアの主導権を自分に取り戻そうとしています。
- 今までやってきたことを記録する
- 自分らしい視点を言葉にしてみる
- 得意が“あるかないか”ではなく、“見えてきたかどうか”に目を向ける
中級の壁を越えるヒントは、遠くにある“理想の誰か”ではなく、目の前にいる、今の自分の中にあるのだと思います。

私自身、「得意がない」「なんでも屋なだけで、これといった強みがない」と感じて、何度もモヤモヤと向き合ってきました。でもそれって、きっと私だけじゃなかったんだなと、たくさんの方と話して気づきました。
“得意がない”という状態は、足りないわけじゃなく、まだ言葉にできていないだけかもしれません。 それを「整えて」「育てていく」ことも、立派なキャリアの築き方なんだと思っています。
もし今、「自分にはこれといった武器がない」と感じていても大丈夫です。 あなたの中には、すでに“強みのタネ”があるはず。 この記事が、その存在に気づく小さなきっかけになれたらうれしいです。
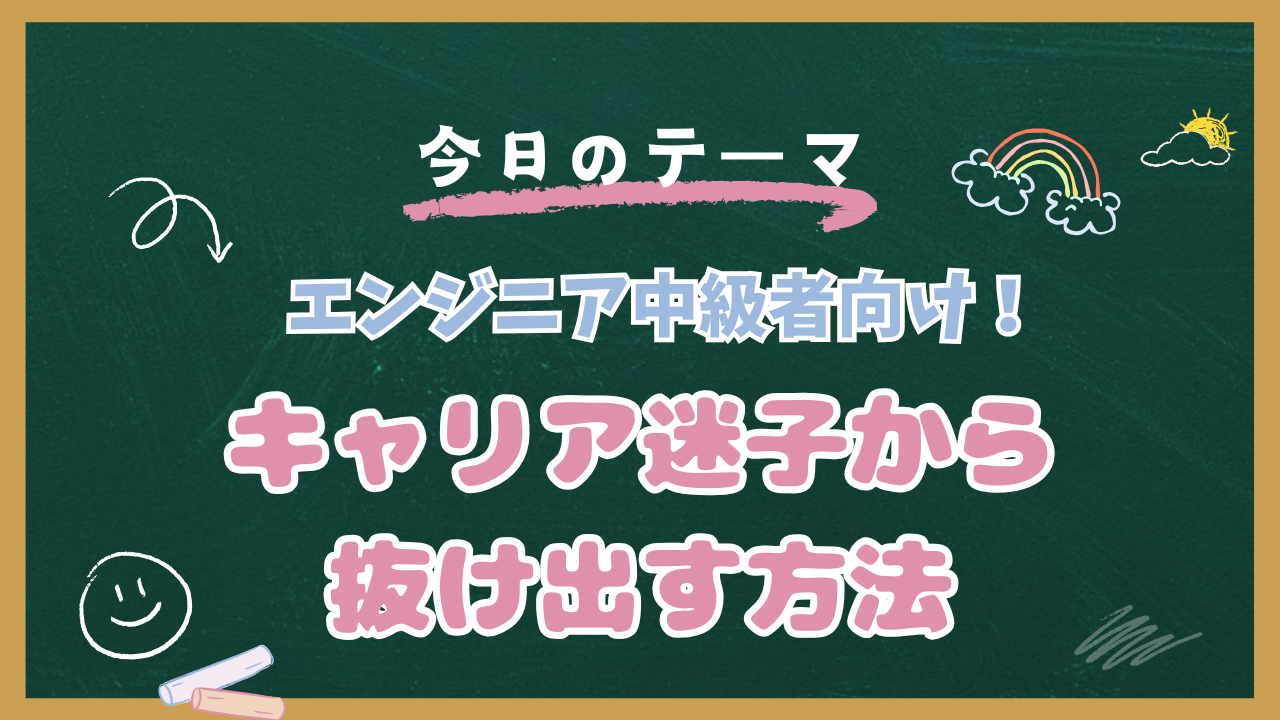
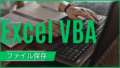

コメント