数年前、自分が書いたSQLを見返して、思わずそっとウィンドウを閉じたことがあります。
「WHERE句、どこ行った?」
「なぜこのJOINはこんなにも…情緒不安定?」
と、自分へのツッコミが止まりませんでした。
あれはもう、未来の自分からの軽い復讐だったのかもしれません。
一方で、ある日見せてもらった同僚のSQLがとても衝撃的で——
なんて、読みやすいんだ!まるでエッセイのようにスラスラと頭に入ってくる構造美。
SQLに「美しい」なんて感情を抱くとは、正直思ってもみませんでした。
その瞬間から私は、「動けばいい」ではなく「読みやすく、未来の自分や仲間にやさしいSQLを書きたい」と思うようになりました。
この記事では、そんな私の反省と発見をもとに、可読性の高いSQLを書くためのベストプラクティスを、わかりやすくご紹介します。
「え、SQLってそんな気をつかうものなの?」と思っている方にこそ読んでいただきたい内容です!
そのSQL、未来のあなたが読めますか?
SQLって、書く瞬間は“完璧だ”と思うんですよね。
脳内ではデータの流れもロジックもバッチリ理解しているし、今なら誰にでも説明できそうな気がする。
…でも、不思議なことに、3日後の自分ですら読めないことがある。
たとえば、数年前の私はこうでした。
SELECT u.id, u.nm, p.pr, o.od
FROM u, p, o
WHERE u.i = p.ui AND o.pi = p.i AND o.d > '2022-01-01'「省略しすぎィィ!」と今なら突っ込みたい。
uって誰だよ、nmって?と。
このときは、「自分だけが見るから」と思ってつけた謎エイリアスや短縮形が、あとになって暗号と化すなんて思いもしませんでした。
一方で、私の同僚が書いたSQLはまるでガイドブックのようでした。
SELECT
users.id,
users.name,
products.price,
orders.order_date
FROM
users
INNER JOIN products ON users.id = products.user_id
INNER JOIN orders ON products.id = orders.product_id
WHERE
orders.order_date > '2022-01-01'どこからデータが来て、どう結合され、何を抽出したいのかが一目でわかる。
これはもう設計図というより、ストーリーでした。
「SQLってこんなに親切に書けるのか…」と感動したのを今でも覚えています。
読みやすさは、未来の自分とチームへの“ラブレター”
「動けばいい」「ちゃんと結果出てるからヨシ!」。
その気持ち、すごくわかります。特に時間がないときはなおさらです。
でも、数週間後にバグ修正でそのSQLを見直すとき、あるいは別の人が保守するとき、“読みやすさ”があれば、どれだけ時間と心を救えるかを知ってから、私は考えを改めました。
読みやすさ=丁寧なフォーマット、適切な命名、構造の整理。
どれも一見地味ですが、積み重なると「おっ、このSQLわかりやすいな」って信頼されるようになります。
この章では、“読みやすいSQL”の重要性を私の体験も交えてお話しました。
次の章からは、具体的にどこをどう書けば読みやすくなるのか?
実際のテクニックとともに、現場で活きる書き方を一緒に見ていきましょう!
基本のフォーマットルールを整えよう
SQLの可読性を高める第一歩は、「見た目を整えること」です。
処理の正確さやロジックももちろん大切ですが、パッと見て構造が理解できるかどうかで、読む側のストレスは大違い。
ここでは私自身も心がけている、読みやすいSQLを書くためのフォーマットルールをご紹介します!
インデントと改行で、流れを見える化!
読みやすいSQLは、まるで物語のように“流れ”が伝わります。
その鍵はインデントと改行の使い方。以下の2つを比べてみてください。
❌ 読みにくい例:
SELECT u.id, u.name, o.total FROM users u INNER JOIN orders o ON u.id = o.user_id WHERE o.status = 'completed' AND o.total > 1000;⭕️ 読みやすく整えた例:
SELECT
u.id,
u.name,
o.total
FROM
users u
INNER JOIN orders o ON u.id = o.user_id
WHERE
o.status = 'completed'
AND o.total > 1000;改行してブロックごとに揃えてあげると、「SELECTで何を取りたいのか」→「どのテーブルを使っているのか」→「条件は何か」という流れがクリアになります。
特に複数のJOINやサブクエリがある場合は、整っているだけで理解速度がまるで違います。
SQLキーワードは大文字?それとも小文字?
これは開発現場によって流派が分かれる部分ですが、SQLの予約語(SELECT、FROM、WHEREなど)は大文字、それ以外は小文字という書き方が一般的です。
SELECT
id,
name
FROM
users
WHERE
is_active = true;こうすることで、「SQLキーワード」と「テーブルやカラム名」が視覚的に分離されて、読みやすさがぐっと上がります。
もちろん一貫していれば全部小文字でも構いませんが、チームで書くならルールを統一するのが吉です!
コメントは未来の自分への手紙
SQLは「何をしているか」は読めても、「なぜこの条件にしたのか?」は書いていない限り伝わりません。
少しでも複雑な処理を書いたときは、一行でもいいのでコメントを残しておくと未来の自分が助かります。
-- 商品価格が1,000円以上かつ、キャンペーン中の注文のみを取得
SELECT
*
FROM
orders
WHERE
price >= 1000
AND is_campaign = true;特に業務上のビジネスロジックが絡むときほど、コメントが「ドキュメント代わり」になります。
ほんの一言が、数週間後の自分を救うかもしれません…(というか、私は何度も救われました)。
一貫性がすべてを整える
「読みやすいSQL」は慣れ親しんだパターンであることが多いです。
つまり、インデントやキーワードの大文字・小文字、カラムの並び順などをブレなく書き続けることが、読みやすさにつながります。
おすすめは、チームでSQLフォーマットの簡単なルールを決めておくこと。
それだけで「誰が書いたSQLでもすんなり読める」環境ができますし、レビューのときにもコメントが減るので、精神衛生にもやさしいです。
この章では、SQLを「論理」ではなく「見た目」から整えるテクニックを紹介しました。
次の章では、「ありがちな読みにくいSQL」のパターンと、どう改善すれば読みやすくなるかを実例ベースで深掘りしていきます。
ぜひ一緒に“Before → After”で見ていきましょう!
よくある「読みにくいSQL」の例と改善パターン
「このSQL、実行はできるけど…読んだら頭痛がしてくる。」 そんな経験、ありませんか?
私は昔、「SQLは短くてコンパクトな方が効率的!」と信じていた時期がありました。
結果、謎の変数、複雑なネスト、空気を読まないJOINで、未来の自分を泣かせるコードが量産されていました…。
この章では、私もやらかしてきた“読みにくいSQLあるある”を例に挙げながら、Before → After 形式で改善方法を紹介していきます!
SELECT句が長すぎて内容が見えない問題
❌ Before(どこに何があるか見えない):
SELECT users.id, users.name, users.email, users.status, users.created_at, orders.order_id, orders.total_price, orders.status
FROM users
JOIN orders ON users.id = orders.user_id;⭕️ After(改行と整列で読みやすく):
SELECT
users.id,
users.name,
users.email,
users.status,
users.created_at,
orders.order_id,
orders.total_price,
orders.status
FROM
users
JOIN
orders ON users.id = orders.user_id;コメント: 項目が多いときは素直に縦に並べた方が、レビューも目視確認もしやすいです。個人的には「読みやすさ優先!」と決めてから、横一列で書くスタイルとはお別れしました。
テーブルの別名が謎すぎる問題
❌ Before(aとかbじゃ何が何だか):
SELECT a.id, b.amount
FROM t1 a
JOIN t2 b ON a.i = b.ai;⭕️ After(エイリアスも意味ある名前に):
SELECT users.id, payments.amount
FROM users u
JOIN payments p ON u.id = p.user_id;コメント: 書いてるときは「省略してスッキリ!」なんて思ってましたが、それが混乱のもと。エイリアスは短くても、意味が伝わるようにするのがコツです!
JOINが複雑で「迷子になる」問題
❌ Before(読んでて疲れるJOIN構造):
SELECT *
FROM a
JOIN b ON a.id = b.a_id
JOIN c ON b.id = c.b_id
JOIN d ON c.id = d.c_id
WHERE d.status = 'active';⭕️ After(JOINごとに意味を整理・分ける):
SELECT
a.*,
b.*,
c.*,
d.status
FROM
customers a
JOIN
orders b ON a.id = b.customer_id
JOIN
shipments c ON b.id = c.order_id
JOIN
delivery_status d ON c.id = d.shipment_id
WHERE
d.status = 'active';コメント: テーブルの役割が分かるように名前を見直すだけで、JOINが物語のように読めるようになります。私はこれで「JOINにビビらなくなりました」!
WHERE句や条件がぎゅっと詰まりすぎ問題
❌ Before(判定がどこからどこまでか分からない):
WHERE status = 'active' AND start_date <= NOW() AND (end_date >= NOW() OR end_date IS NULL)⭕️ After(論理ブロックで分けて見やすく):
WHERE
status = 'active'
AND start_date <= NOW()
AND (
end_date >= NOW()
OR end_date IS NULL
)コメント: これだけでもだいぶスッキリ。「脳内で括弧を補完しながら読む」ストレスが軽減されます。SQLにおける“適度な改行”は、読み手へのやさしさ。
サブクエリがネストしすぎて精神が試される問題
❌ Before(中で何やってるのか分からない):
SELECT * FROM (
SELECT * FROM (
SELECT user_id, COUNT(*) FROM orders GROUP BY user_id
) AS sub1
) AS sub2;⭕️ After(CTEで段階的に見せる):
WITH order_count AS (
SELECT
user_id,
COUNT(*) AS total_orders
FROM
orders
GROUP BY
user_id
)
SELECT
*
FROM
order_count;コメント: CTE(WITH句)を使うと、「処理の段階」ごとにSQLを分けられて、頭の中も整理しやすくなります。“途中の結果に名前を付けられる”ってすごくありがたい!
この章では、ありがちな「読みにくい書き方」と「それをどう改善するか」を比較してみました。
どれも「ちょっとした気遣い」レベルの改善ばかりですが、積み重なるとSQLが一気に読みやすく、安心感のあるコードに育ちます。
次の章では、命名や別名(エイリアス)の工夫について深掘りしていきますよ。
変数名やテーブル名は、「読む人へのメッセージ」なのです!
意図が伝わる命名と別名(エイリアス)の付け方
SQLを書いていると必ず出てくるのが「テーブル名やカラム名、そして別名(エイリアス)をどう書くか問題」です。
これ、想像以上に可読性を左右する重要ポイントなんですよね。
エイリアスに「意味」を持たせよう
短く書けるからといって、何でも a, b, c にしていませんか?
私はしてました。というか、昔は「SQLってそうやって書くもの」だと思ってました。
-- ❌ エイリアスが謎すぎる
SELECT a.id, b.name
FROM t1 a
JOIN t2 b ON a.i = b.ai;これ、当事者じゃないと何が何だかさっぱりです。
少し長くてもいいから、“見ただけで役割が想像できる名前” にすると、理解力が格段に上がります!
-- ⭕️ 意味のあるエイリアス
SELECT customer.id, product.name
FROM customers AS customer
JOIN products AS product ON customer.id = product.customer_id;“これ、あのテーブルだな”と脳内変換するコストが減るだけで、読みやすさは爆上がりします。
曖昧なカラム名は、プレフィックスで役割を明確に!
JOINを多用するSQLでは、複数のテーブルに同じ名前のカラムが存在することもよくあります。
たとえば id や name など。
こういうとき、どのテーブルのカラムなのかを明示することが大切です。
-- ❌ どのidだよ問題
SELECT id, name FROM users JOIN orders ON id = user_id;-- ⭕️ プレフィックスですっきり
SELECT users.id AS user_id, orders.id AS order_id, users.name
FROM users
JOIN orders ON users.id = orders.user_id;読み手にとって「このidは誰の?」という混乱を防ぐだけでなく、保守やバグ調査でもスムーズに追跡できるという大きな利点があります。
命名のルールは「未来の自分が読めるか」を基準に
変数名やエイリアスに関しては、短ければいいというわけではなく、“書いたそのときの自分以外が読んでも理解できるか?” を意識するのがコツです。
| 曖昧な命名 | 意図が伝わる命名 |
|---|---|
| t1, t2 | customer, order |
| id, dt | user_id, purchase_date |
| x, y | price_total, shipping_fee |
現場では「短く!簡潔に!」という風潮もありますが、読みやすさと意味の伝わりやすさはトレードオフではなく、両立できるのです。
名前に“会話できる”感覚を持たせよう
私の中でひとつの基準は、「名前を見たとき、自然に読めるかどうか」。
u.id = o.uid よりも、users.id = orders.user_id のほうが、「ユーザーとオーダーの関係」が自然に伝わりますよね。
読み手と会話しているようなSQLを書くことが、“共有されるコード”としての完成度を高めてくれると思っています。
この章では、SQLに登場する名前たちに「意味」と「会話性」を持たせることの大切さを紹介しました。
命名のセンスは慣れと観察から磨かれます。
最初はちょっと面倒でも、「伝わる名前」を意識して書いてみると、読みやすさだけでなく、コードとしての信頼感もグッと上がるはずです。
次の章では、「WHERE句や論理演算の整え方」について、一歩踏み込んだ整理術をご紹介していきます!
条件句や論理演算の整え方
SQLにおける「読みやすさ修行」のなかで、多くの人が頭を抱えるのがこの部分。
そう、WHERE句とAND/OR地獄です。
ぱっと見、シンプルに見えても、条件が3つ、4つと増えてくると「これ、ちゃんと正しく動いてるの?」と自信がなくなってきます。
そして、ANDとORが混ざった瞬間、「読めない」「信じられない」「もう書きたくない」の三拍子がそろうわけです(体験談)。
WHERE句は“段落”で整理する
まず前提として、条件が多くなる場合は、無理して1行に詰め込まない! が鉄則です。
❌ 読みにくい例:
WHERE status = 'active' AND start_date <= NOW() AND (end_date IS NULL OR end_date >= NOW()) AND region = 'JP'⭕️ 読みやすい例:
WHERE
status = 'active'
AND start_date <= NOW()
AND (
end_date IS NULL
OR end_date >= NOW()
)
AND region = 'JP'改行とインデントで「論理のまとまり」を見える化するだけで、処理の意図がスーッと入ってくるようになります。
脳内でカッコを想像しなくて済むんです。
ANDとORの混在は“明示的なグループ化”で防御する
SQLの世界では、ANDがORよりも優先されます。
…が、それを理解していても、いざ複雑な条件を読むと「えっと、これどこからどこまで?」と混乱すること、ありますよね。
だからこそ、カッコ(括弧)を使って優先順位を明示するのが読みやすさのコツ。
⭕️ 例:明示的にグループ分けする
WHERE
product_type = 'subscription'
AND (
cancel_date IS NULL
OR cancel_date >= CURRENT_DATE
)これなら「今も有効なサブスクリプション」を取りたいんだな、という意図がすぐに読み取れます。
“書いた人だけがわかるSQL”にならないように、明確な構造をつけてあげましょう。
NULLの判定こそ読みやすさの落とし穴
SQLには“NULLは比較できない”という独特のルールがあります。
これが読みづらさやミスの温床になることも。
-- ❌ 誤:これだとNULLは評価されません
WHERE updated_at != '2023-01-01'
-- ⭕️ 正:NULLも考慮するならこう書く
WHERE updated_at IS DISTINCT FROM '2023-01-01'または条件にNULLを含めたいときも明示しましょう:
WHERE status = 'active' OR status IS NULL隠れたNULLトラップに気づかせてくれるのは、丁寧な表現と読みやすい構造だったりするんです。
条件には“意味のまとまり”を意識する
複雑な条件が増えてくると、「意味で分ける」という感覚が役立ちます。
たとえば:
-- ステータス判定
AND status = 'active'
-- 日付による有効判定
AND start_date <= CURRENT_DATE
AND (
end_date IS NULL
OR end_date >= CURRENT_DATE
)こうして“見た目の段落”で整理しておくと、何を判定しているSQLなのかが自然と伝わってきます。
私自身、「あ、構造で読めばいいんだ」と気づいてから、WHERE句への恐怖心がぐっと減りました。
この章では、「読める条件句」のために使える構文テクニックと考え方をご紹介しました。
ロジックが増えても、きれいに読めるように整えておくことが、可読性の高いSQLの肝になります。
次の章では、ややレベルアップして「サブクエリ vs CTE(WITH句)」を比較しながら、“迷路のようなSQL”をどう整えるかについてお話していきます!
サブクエリ vs CTE(WITH句)、どっちが読みやすい?
SQLを書いていると、サブクエリが必要な場面ってよくありますよね。 で
も、気づいたら FROM (SELECT … FROM (SELECT …)) のような三重構造になってしまって、「あれ、今何やってるんだっけ?」と混乱した経験、ありませんか?
この章では、そんな“サブクエリあるある”を読みやすく整えるために便利な CTE(Common Table Expression:通称WITH句) を取り上げて、 「それぞれどう使い分けるといいのか?」を初心者の方向けにわかりやすく解説します!
サブクエリの良さと、ハマりやすい罠
サブクエリは、SQLのなかで処理を内包する強力な手段です。
たとえば:
SELECT
id,
name,
(SELECT COUNT(*) FROM orders WHERE orders.user_id = users.id) AS order_count
FROM
users;これは読みやすくてシンプルなサブクエリの例。
でも、複雑になってくると……
SELECT *
FROM (
SELECT user_id, MAX(purchase_date) AS last_purchase
FROM (
SELECT user_id, purchase_date
FROM orders
WHERE status = 'completed'
) AS sub1
GROUP BY user_id
) AS sub2;ネストが深くなるほど、頭の中もSQLもカオス化してしまいます。
CTE(WITH句)を使って、構造を“分かりやすく”分ける!
そんなときに役立つのがCTE。
まるで“途中式に名前をつけて分解する数学”のように、SQLの構造を段階的に整理できます。
上のクエリ、CTEを使うとこうなります:
WITH completed_orders AS (
SELECT user_id, purchase_date
FROM orders
WHERE status = 'completed'
),
last_purchase_per_user AS (
SELECT user_id, MAX(purchase_date) AS last_purchase
FROM completed_orders
GROUP BY user_id
)
SELECT *
FROM last_purchase_per_user;どうでしょう? 一段階ずつの処理が名前付きで切り分けられていて、処理の意図が一目瞭然。
「まず完了した注文を選んで、そのあとにユーザーごとの最新購入日を集計してるんだな」という流れが、読者の脳内に地図のように描けるわけです。
じゃあ、全部CTEで書けばいいの?
…と思うかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
CTEは読みやすさを優先する場合に特に力を発揮しますが、場合によってはパフォーマンスが落ちることもあります(PostgreSQLではCTEが「使い回されない」ため)。
そのため、
- 再利用の必要がない1回限りの処理
- ごく短いロジック
であれば、サブクエリの方がシンプルで読みやすい場合もあります。
要は、「読む人がどう感じるか」視点で選択するのがベスト!
実務の中での使い分けポイントまとめ
| シーン | サブクエリが向いている | CTEが向いている |
|---|---|---|
| ネストが浅い | ◯ | △ |
| 処理を段階で分けたい | △ | ◯ |
| 再利用する処理がある | △ | ◯ |
| パフォーマンスが厳しい処理 | ◯(インライン最適化あり) | △(PostgreSQLは最適化しづらい) |
| チームや将来の自分が読む可能性が高い | △ | ◯ |
CTEは“読みやすさ重視の味方”ですが、すべてをCTEで書く必要はありません。
あくまで道具として、目的に応じて使い分けていくことが重要です。
この章では、サブクエリとCTEの違いと使いどころを整理しました。
次の章では、実際の業務でありがちな“長くて混乱しがちなSQL”をBefore→Afterでリファクタリングする実践編に入っていきます!
実践編:ありがちな“読みにくいSQL”を整えてみよう
ここまで、読みやすいSQLを書くための考え方や構文テクニックを紹介してきました。
この章では、実際にありがちな“モヤっとするSQL”を見て、どう直すと読みやすくなるかをBefore → After形式で体感してみましょう!
ケース①:全部1行に詰めたら誰も読めない問題
❌ Before:
SELECT u.id, u.name, o.total FROM users u JOIN orders o ON u.id = o.user_id WHERE o.status='completed' AND o.created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days';⭕️ After:
SELECT
u.id,
u.name,
o.total
FROM
users u
JOIN
orders o ON u.id = o.user_id
WHERE
o.status = 'completed'
AND o.created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days';コメント: 改行+整列によって、処理の意図が段階的に伝わるように。読み手の脳内を圧迫せず、SQLが“説明書”のようになるのが理想です!
ケース②:JOINが多すぎて構造が読めない問題
❌ Before:
SELECT * FROM users u JOIN orders o ON u.id = o.user_id JOIN shipments s ON o.id = s.order_id JOIN delivery_status d ON s.status_id = d.id WHERE d.name = 'delivered';⭕️ After:
SELECT
u.*,
o.*,
s.*,
d.name AS delivery_status
FROM
users u
JOIN
orders o ON u.id = o.user_id
JOIN
shipments s ON o.id = s.order_id
JOIN
delivery_status d ON s.status_id = d.id
WHERE
d.name = 'delivered';コメント: JOINの段階を改行で区切り、テーブルごとの役割が見えるようにすることで、“つながりの流れ”が自然と読めるSQLになります。
ケース③:複雑な条件がぐちゃっと詰まっている問題
❌ Before:
SELECT * FROM users WHERE is_active = true AND (last_login > CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days' OR role = 'admin') AND region = 'JP';⭕️ After:
SELECT
*
FROM
users
WHERE
is_active = true
AND (
last_login > CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
OR role = 'admin'
)
AND region = 'JP';コメント: ANDとORが混在するときは“明示的にグループ化する”のが鉄則です! ロジックの見通しがよくなるだけでなく、間違った意味で解釈される事故を防ぐことにもつながります。
ケース④:サブクエリが深すぎて酸欠になる問題
❌ Before(ネストが深くて読めない):
SELECT user_id, total
FROM (
SELECT user_id, SUM(price) AS total
FROM (
SELECT user_id, price
FROM orders
WHERE status = 'completed'
) AS sub1
GROUP BY user_id
) AS sub2;⭕️ After(WITH句で分解):
WITH completed_orders AS (
SELECT user_id, price
FROM orders
WHERE status = 'completed'
),
user_totals AS (
SELECT user_id, SUM(price) AS total
FROM completed_orders
GROUP BY user_id
)
SELECT
user_id,
total
FROM
user_totals;コメント: 処理を段階ごとに分けて見せることで、SQLが「読める物語」になる感覚が得られます。CTE、やっぱり頼りになります。
この章では、「読みにくいけどありがち」なSQLをもとに、どう書き直せば見通しがよくなるかを実践的に見てきました。
ときには“ちょっと書く手間”が増えるかもしれません。
でもその先にあるのは、未来の自分が「うわ、読みやすい!」と感動するSQLです。
次章では、これまで紹介してきた知見をまとめつつ、さらに学びを深めたい人への“次の一歩”をご提案します!
まとめ:可読性は“未来の自分への思いやり”
「SQLなんて、ちゃんと動けばいいでしょ?」 そう思っていた時期、私にもありました。
むしろ「短く書いたほうがカッコいい」とすら思っていたくらいです。
でも、いざ数カ月後にそのSQLを自分で読み直すと、 「これは…どこの誰が書いた暗号文…?」 とフリーズ。
まさか自分の手によるものだったとは。
そこから私は気づきました。可読性って、未来の自分へのやさしさなんだなって。
書き方ひとつで、チームの安心感が変わる
この記事では以下のような視点で、読みやすいSQLを書くためのベストプラクティスを紹介してきました:
- インデントや改行で構造を“見える化”する
- 別名には意味を込めて、変数感覚で使う
- 条件句は論理ブロックごとに整理して、AND/ORは明示的にグループ化する
- サブクエリやネストが深くなりそうなら、CTEで分割する
- 自分にしか伝わらないコードじゃなく、仲間にも伝わる構造を意識する
こうした小さなテクニックの積み重ねが、読みやすさ・保守しやすさ・チームでの信頼につながっていくんですよね。
“未来のあなた”と会話できるSQLを書こう
SQLはただのデータ取得ツールではなく、人と人をつなぐコミュニケーションの手段です。
あなたのSQLを読む人は、明日の自分かもしれないし、隣の同僚かもしれない。
だからこそ、「読み手」の存在を意識した書き方が大切なのだと思います。
最後に
読みやすさを意識したSQLは、それだけで価値のある技術です。
スキルというよりも、姿勢や習慣に近いものかもしれません。
この記事が、あなたのSQLにちょっとした“整える楽しさ”を届けられたならうれしいです。
さあ、次にSQLを書くとき、ちょっとだけ“未来のあなた”のために気を配ってみませんか?

自分の過去のSQLを見て「これは…誰の仕業?」と頭を抱えた経験から、この記事を書きました。
「SQLは動けばヨシ」——そう思っていたあの頃の私に、そっと手紙を書くような気持ちで、 「読みやすさって大事なんだよ」と伝えたかったんです。 そして今、この記事があなたの学びのヒントになっていたなら、こんなに嬉しいことはありません。
もしどこかで、”ちょっと読みやすく書いてみようかな” と思ってもらえたら、 それはこの先のあなたの未来の自分やチームメイトへの、最高の思いやりだと思います。
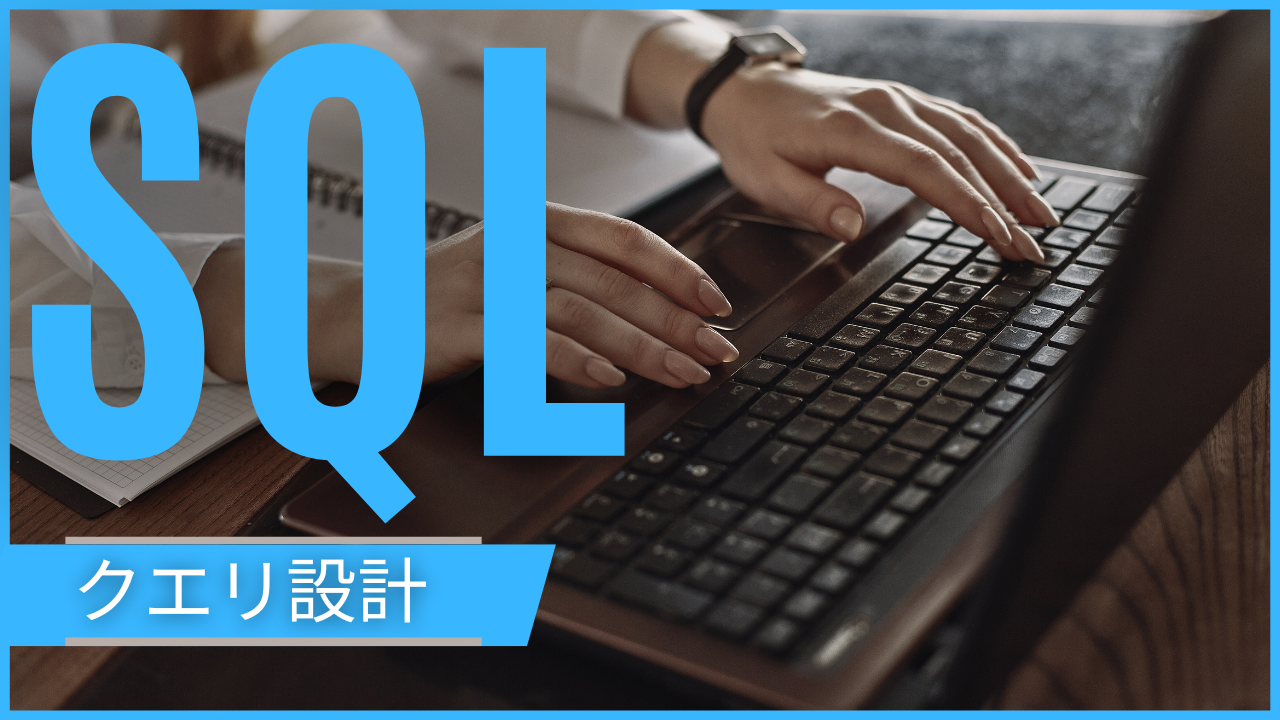
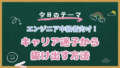

コメント