調べたのに、また調べてる問題
「あれ、このエラー前にも出たな…」
「えっと、あの便利なコマンドなんだっけ?…ググろ」
…そうして気がつくと、数日前の自分とまったく同じ検索をしていることってありませんか?
私はあります。もう何回目かもわかりません。
まるで未来の自分から「また会ったな」って言われているような気さえします。
でも、これって私だけじゃないと思うんです。
エンジニアという生き物、調べて学び、すぐ忘れ、また調べる——
これを繰り返して進化していく…そう、ポケモン方式です(?)
とはいえ、せっかく調べたなら“一回きりの知識”ではなく、“使える知識”として手元に残したい。
そのために私自身が模索してきたのが、「検索後の情報整理&軽いアウトプット」という習慣でした。
この記事では、 「調べて→忘れて→また調べる」無限ループを抜け出し、 調べたことをしっかり定着&活用できるテクニックを、 ゆるめなトーンでお届けします!
検索力を「ぐぐる力」で終わらせず、「育てる力」へ。
今日からあなたの学びも、一歩アップグレードしてみませんか?
情報は“貯め方”次第で身につかない|なぜ覚えられないのか?
「前に調べたはずなのに、内容がスルッと抜けてる…」 そんな経験、エンジニアなら一度はあるのではないでしょうか。
どれだけ熱心に調べても、しばらくすると記憶の海に沈んでいく知識たち。
なぜこんなにも「調べたのに覚えてない」現象が起きるのでしょうか?
原因その1:「点」で覚えて、「線」にできていないから
たとえるなら、検索で得た知識は“単語カード”のようなもの。
それ自体は意味を持っていても、文脈や他の知識とつながっていなければ、すぐに忘れてしまうのです。
- 例: git stash の使い方はググったことがある → でも「いつ」「なぜ」使うのかがわからない → 結局また検索。
つまり、“点の知識”だけでは、いざというときに活用できないんですね。
原因その2:「受け身の検索」になっていませんか?
私たちは検索によって、知識のショートカットを手に入れがちです。
ただし、調べる→読む→閉じる では「脳に残る時間」が非常に短い。
これが、
- 「ページを開いた記憶はある」
- 「スクロールもした気がする」
- 「でも結論はまったく覚えていない」
の三重苦につながります。
本当に覚えたいなら、「なぜこうなるのか?」「ほかのケースは?」と一歩踏み込んだ検索をすることが大事なんです。
原因その3:「使っていない知識」は脳に“捨てられる”
人間の脳は、使われない情報は“重要じゃない”と判断して自然に整理してしまいます。
つまり、検索して得た知識もアウトプットや再利用されないと記憶に定着しにくいんです。
- 調べた → わかった気になる → 実践で使う前に忘れる → 再検索
この無限ループ、よくありませんか?私は2ループくらいしてから「これは記録すべき」と気づくタイプです。
だからこそ、「検索+整理+軽いアウトプット」が必要
情報は“貯め方”を間違えると、いくら調べても「使える知識」にはなりません。
覚えられない最大の原因は、“自分の頭で整理していない”から。
次章からは、
- 情報をどう整理すれば定着するのか
- どんなふうにアウトプットすると学びが深まるのか
を、私の工夫を交えながらご紹介していきます!
「調べたら終わり」から、「調べたら育てる」へ。
一緒に検索スキルを“知識活用力”へと進化させていきましょう!
知識はアウトプットしてこそ定着する|情報整理×出力の原則
さて、前章で「調べただけじゃ忘れる」問題についてお話ししました。
ここからは、その解決法となる「アウトプット」と「情報整理」の話に入っていきます。
「調べたことをちゃんと覚えたい」
「次に活かせるように残したい」
そんなときに必要なのは、少しの手間と軽い書き出しだったりします。
そう、完璧なノートじゃなくてもいいんです。
情報は「見た」だけでは脳に残らない
まず大前提として、人間の脳は「受け身」で得た情報をすぐに忘れます。
つまり「読んだだけ」「スクショだけ」「ブックマークだけ」では、理解した気分にはなれても、実際には定着していないんです。
- 「見た記憶はあるけど、どこに書いてたっけ?」
- 「あのQiita記事、どのキーワードで見つけたんだっけ…?」
思い出せない。それは、自分の中で“再構築”していないからなんですね。
「アウトプット=記録」ではなく「思考の整理」ツール
「アウトプット」と聞くと、 「ちゃんとしたブログにしなきゃ」とか「誰かに教えられるレベルじゃないし…」と思いがちですが、そんな必要はありません!
アウトプットとは、自分の頭の中で“情報の並び替え”をする作業なんです。
たとえば…
- 「このエラー、なぜ起きたんだろう?」→「原因を1文で書いてみる」
- 「公式ドキュメントにこう書いてた」→「つまり、こういうことだよね?」と自分の言葉で再表現
- 「3種類のオプションがある」→ 表で比較してみる
これだけでも立派なアウトプット!
情報を“自分の文脈に通す”ことで、理解度も記憶への定着も段違いになります
オススメ:3分アウトプット習慣(気負わず書く練習)
私がよくやっているのは、「調べ終わったら3分だけ書いてみる」習慣です。
Notionでも、紙のメモ帳でも、Slackの自分チャンネルでもOK。
たとえばこんなふうに
できたこと:SQLのGROUP BYでハマったエラーを解決
学んだこと:ORDER BYとの併用でグループ化の順序に影響あり
覚えておきたい:この件、PostgreSQLとMySQLで挙動が微妙に違うので注意
後で見返すと「この時こんなこと調べてたんだ」と復習にもなるし、 何より記憶の“タグ”が脳に残る感じがします。
情報整理のコツは「手を動かしながら考える」こと
完璧にまとめようとするからハードルが上がるんです。
「書きながら考える」「散らかっててもいいからメモする」ことで、 頭の中の“もやもや”が“知識のかたまり”に変わっていきます。
大事なのは、完璧さより「行動量」。
脳にとっては「とりあえず形にしたもの」から順に記憶が強くなっていくんです。
まとめ:「検索→整理→ちょい出力」で記憶に残る
- 「読んだだけ」より「書いた方が、覚える」
- 1文でもいい、ツッコミでもいい、自分の言葉で再表現すること
- アウトプット=“記憶のためのメモ”だと思えばOK!
次章では、そのアウトプットをもっとラクに、もっと見やすく整理するための情報整理テクニック&ツールの活用術をご紹介します。
学びが加速する情報整理テクニックとツール活用法
調べたことを記憶に残したい。
記録した情報を、あとで再利用したい。
でも、ノートは散らかるし、ブックマークは「迷子ランド」状態…。
そんなあなた(=過去の私)に贈るのが、情報を「引き出せる形」で残す整理術です。
この章では、「あとから見返して役立つ」「知識がつながっていく」整理のコツと、実際に使えるツールや方法をご紹介します!
整理術その1:タグ・ラベルで「使うときにすぐ出てくる」仕組みをつくる
まずは超基本。でも超大事。
どこに何を置いたか分かるようにしておく、これが整理の第一歩です。
- ❌:「Python」って入ってるけど内容はフレームワーク比較→再発見困難
- ⭕️:「#Python #FastAPI #認証」→ 検索しやすい!見つけやすい!
NotionやObsidianなどのツールでは、タグ・リンク・カテゴリ分けが使えるので、 情報に“検索可能な引き出し”をつける意識で整理してみましょう。
整理術その2:「リンクでつなぐ=脳内マップをつくる」技
1つの知識を、他の知識とつなげておくことで、思い出しやすさが段違いに上がります。
たとえば…
- 「Flask」と「FastAPI」はどう違う?→ 比較ページで相互リンク
- 「PostgreSQLのJOIN最適化」と「クエリチューニング手法」をリンクでつなげる
- 「VBAセル操作メモ」↔「Excel方眼紙への恨みノート」も(?)
こういった“知識のハブ”を意識することで、点と点が線になります。
特にObsidianなど、双方向リンクが使えるツールは知識マップづくりに最適です。
整理術その3:項目テンプレートを用意して、書くハードルを下げる
「記録しなきゃ」と思っても、何を書くか迷うと手が止まりますよね。
そこでおすすめなのが、軽いテンプレートを決めておくこと!
たとえば、私がよく使っている例はこんな感じ
検索キーワード:
なにを調べたか:
わかったこと:
参考リンク:
応用や注意点:
このフォーマットがあるだけで、「とりあえず書いてみよう」が圧倒的にラクになります。
1日1エントリでも積み上げれば、立派なナレッジベースになりますよ。
整理に使えるおすすめツールたち(目的別)
| ツール名 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| Notion | Webクリッピング・タグ付け・共有が万能 | 見た目も使いやすさも両立したい人 |
| Obsidian | ローカル保存・双方向リンクが強力 | Zettelkasten風に知識をネットワーク化したい人 |
| Scrapbox | すぐ書けてすぐリンクできる | 思考と整理を“同時にやりたい”人 |
| Google Keep / メモ帳 | まずはライトに試してみたい | 気楽にアウトプット習慣を始めたい人 |
「どれが最強か」ではなく、“自分が続けられるか”が大切です。
途中で道具を変えるのも全然アリ。
道具を育てるより、習慣を育てるほうが大事なんです。
まとめ:「あとから使える情報」は“ちょっとの整理”で作られる
- 「タグやリンク」で脳の引き出しを真似する
- 「書き方テンプレ」で習慣化のハードルを下げる
- 「ツール選び」は正解探しより相性探し
次章では、この整理した情報をどのタイミング・どんな形で発信していくと、 「学びを最大化できるか?」という、アウトプット編に進んでいきます。
どこまで発信すべき?アウトプットの3段階モデル
「学んだことを発信しましょう」ってよく聞くけれど、 いざ何か発信しようとすると…
- 「このレベルで書いていいのかな…」
- 「正しいか自信ないし…」
- 「こんなの、需要ある?」
…ってなりますよね。私はなります。
でも実は、アウトプットには“段階”があるんです。
いきなり世に向けて発信しなくてもよくて、自分の中での「書く→整える→伝える」というステップを踏めば、それだけで記憶定着も深まるし、情報も再利用できる。
この章では、アウトプットを「クローズド」から「パブリック」まで、3段階に分けて整理する考え方をご紹介します!
第1段階:クローズドメモ(自分だけが見る用)
これは一番手軽で、ハードルが低いアウトプット。
自分のためだけのメモ書きでOKです。Notion、Obsidian、紙のノート、何でも大丈夫。
- 今日調べたこと、ハマったこと、気づき
- 解決法だけじゃなく「どうやって調べたか」もメモっておく
- 書き方が雑でも、言葉が足りなくても気にしない!
ポイントは「正確性」や「論理性」よりも、“感情や気づきが残っているうちにサッと記録すること”。
例:「このエラー、2回目。環境はDocker + M1 → “libxyz.so not found”メモ」→ 後で整理するときのヒントになる!
第2段階:セミパブリック(共有するけどゆるめ)
クローズドよりちょっと公開範囲を広げた形。
Slackの自分チャンネル、SNSの下書き、Zennの草稿など、“誰かが見るかも”くらいのグレーゾーンです。
- 軽く整えて、簡単に説明を加える
- 調べたキーワードや参考URLも載せておく
- 間違っても気にせず、「あとで直せばいいや」精神でOK!
他人に向けた文章になると、自分でも「わかってなかった部分」があぶり出されるのが不思議です。
例:「FastAPIでtoken認証が通らない件。header忘れてた」→ Zenn草稿として一旦保存 → いつでも加筆できる!
第3段階:パブリック(記事・投稿として発信)
ある程度まとまったら、技術ブログやQiita、Zennで公開してみましょう!
ここがいわゆる“発信”ですが、完璧である必要はありません。
大切なのは、「何を伝えたかったか」がはっきりしていること。
エラーの解決記録でも、ちょっとしたTipsでも、誰かの“未来の検索結果”になる可能性があります。
- タイトルに「誰向けか」「どんな悩みか」を入れてみる
- 困ったポイント・回避策・結果を書くだけでも価値がある
- 恥ずかしいかも…と思った内容こそ、他の人にはドンピシャなことも!
3段階アウトプットを“行ったり来たり”してOK!
この3段階は階段ではなく、“ぐるぐる回るループ”です。
- 最初はクローズドメモだけでもOK
- たまに「これは共有したいな」と思ったらセミパブリックへ
- 「書くのが楽しくなってきた!」でパブリックに挑戦
何度でも戻っていいし、書いてる途中でレベルを上げても下げても問題なし。
「無理なく続けられる形でアウトプットを回す」ことが、最大の学びになります。
まとめ:「完璧な発信より、“とりあえず書いた”の方が記憶に残る」
- 自分のために書くメモでも、十分アウトプット
- 少し整えたら、仲間やネットにシェアしてみる
- 誰かの役に立つ情報になったとき、それはもう“知識の貢献”
次章では、こうしたアウトプットの“循環”を続けるために、 日常でムリなく続けられる「情報ループの回し方」をご紹介していきます。
「学んだことを自分の血肉にする」ための習慣のつくり方
ここまで「検索するだけ」から一歩進んだ情報整理やアウトプットについてお話ししてきました。
じゃあ、次に待ってる課題は…?
そう、「それを毎日続けるにはどうすればいいのか?」問題です。
知識は“蓄えた量”ではなく“使った回数”で自分の一部になります。
つまり、情報を扱う“習慣”さえ整えば、自然と知識が積み上がっていくんです。
この章では、無理せず続けられて、ちゃんと“血肉化”できる習慣づくりをご紹介します!
習慣1:「検索→メモ→整理→復習」の“知識ループ”を回す
学んだことをスムーズに吸収していくには、情報を一度で終わらせないのがコツ。
おすすめは「調べた→記録した→時間をおいて読み返した」を“ゆるく”繰り返すスタイルです。
たとえば
- その日調べたことを3行くらいでメモ(検索ワード/内容/気づき)
- 週に1回、メモを見返してタグやリンクをつける(ついでに加筆OK)
- 翌週、同じ分野のタスクに出会ったときにメモを再利用
この“ゆる復習リズム”をつくるだけで、知識が「使える形」で定着していきます。
習慣2:「5分だけ書く」アウトプットルールをつくる
「がっつり記事化」となると気が重い日でも、 “5分だけ”何か書くと決めておくと、意外とサクッとアウトプットできるようになります。
たとえば…
- 今日のググったキーワードと理由だけ
- エラーの原因と「やったけど効果なかったこと」メモ
- 「この情報は後で人に話すかも」候補のURLと一言メモ
このアウトプット、他人に見せなくてもOKです。
習慣化すれば、ちょっとずつメモが育って、気づけばそれが記事や資料の種になってたりしますよ。
習慣3:「明日の自分に向けて書く」メンタルシフト
「誰かに見せる」「ちゃんとまとめる」という意識を捨てて、 未来の自分に渡す引き継ぎメモだと思って書くと、気楽になれるし、書くべきことも絞れます。
形式例:
To: 明日の自分へ
- さっき調べた件、PostgreSQLのversion違いで解決
- Qiitaの記事は参考になるけどv14対応じゃなかったので注意
- メモ:Stack Overflowでv14解決例あり(リンク貼った)これだけで、次回同じ壁にぶつかったときに「過去の自分、ありがとう…!」ってなれます。(私は何度も自分に救われています)
継続のコツは「がんばらない設計」にあり
- 完璧に書かなくていい
- まとまらなくても、とにかく一言書く
- 書けなかった日は「今日はパス!また明日」でOK
続けられる仕組みと気持ちの余白が、結果的に“習慣化成功”につながるんです。
まとめ:「知識の習慣化=未来の自分へのプレゼント」
毎日5分でも「検索したことを書き残す」習慣があれば、 あなたの知識は“流れていくもの”から、“積みあがるもの”に変わります。
この章でご紹介した習慣を、自分に合うようにちょっとずつ取り入れてみてください。
「調べたことを自分の血肉にする」感覚、きっと実感できるはずです。

検索についての記事なのに、こんなに長く?と思われたかもしれません。 でも、それだけ「検索」が私たちの学びと日常に深く根ざしている証なのだと思います。私は、「また同じこと調べてる…」と頭を抱えたことが何度もあります。 でも同時に、「これはあのときのエラーと似てるぞ」と気づけたとき、 少しだけ自分が成長した気もして、ちょっと嬉しくなったりするんです。
検索は「できないこと」にぶつかるからこそ生まれます。 そしてそれをきっかけに、「知る」「理解する」「誰かに伝える」という行動が始まります。つまり検索は、伸びしろの入口なのかもしれませんね。
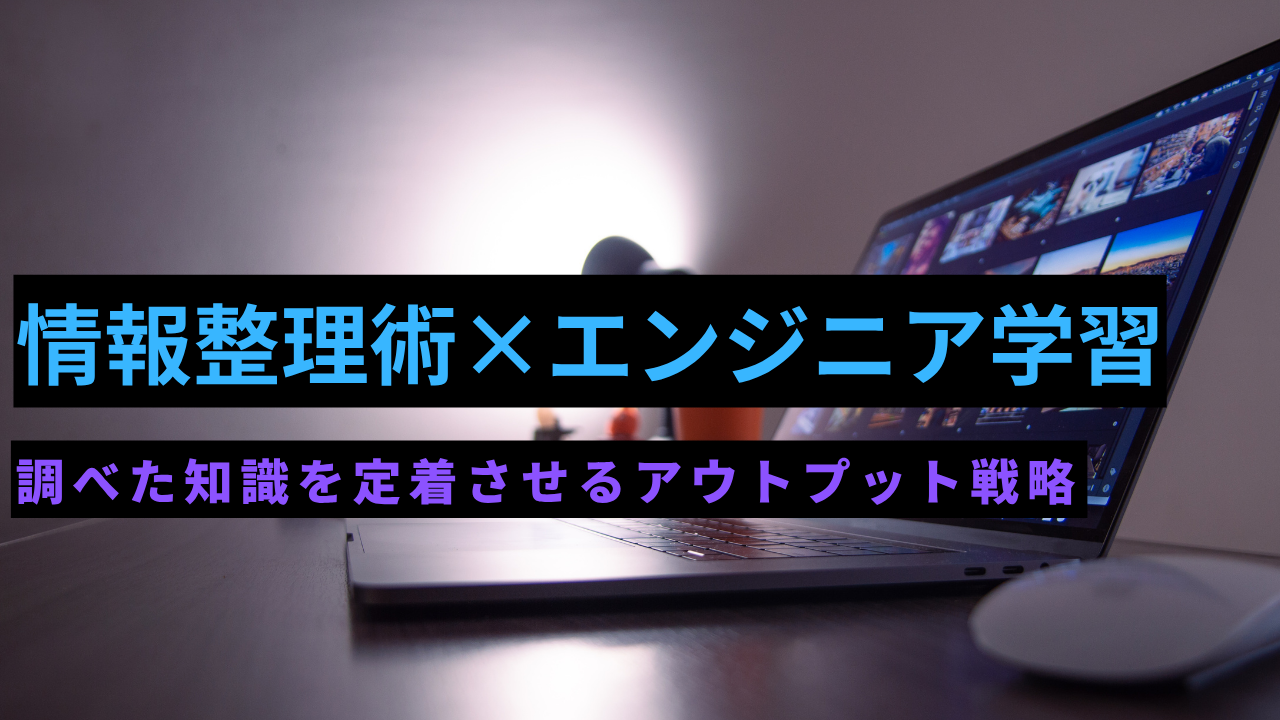

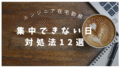
コメント