エンジニアになってGitHubを使うようになった頃は、とにかく「Pushできれば勝ち!」みたいなテンションでした。
黒い画面に打ち込むコマンドが何をしているのかなんて、分かったような、分からないような…。
少しずつ使い慣れてくると、「あれ?これ、ただコード置いてるだけじゃもったいないかも?」と思い始めました。 そんなとき、ふと先輩から言われたんです。
「README、ちゃんと書きましょうね」
そのときの私は、「…リードミー?あの、あの空白のファイルですね?」というレベル。
でも今なら言えます。
READMEは、あなたのコードの“代わりにしゃべってくれる存在”なんです。
この記事では、GitHubで「伝わる技術資料」を作るために、Markdownの基本とREADMEの構成、そして読まれるためのちょっとした工夫をご紹介します。
初心者のころの私に教えてあげたかったこと、ひとつずつ詰め込みました。
なぜREADMEが大事なのか?コードは“声”を持てないから
GitHubにコードをアップすると、それだけで何かすごく「やった感」がありますよね。
でも、いざ誰かにそのリポジトリを見せてみると、こう言われたことはありませんか?
「で、これは何のコードですか?」
それを聞かれた瞬間、ふと我に返るのです。
「…あ、何も説明してなかった」と。
実は、GitHubのリポジトリを訪れる人の多くは、コードの中身より前にREADMEを見ると言われています。
READMEは、プロジェクトの目的や使い方、必要な環境やインストール手順などを伝える場所。
つまりREADMEは、あなたのコードの“代わりにしゃべってくれる存在”なんです。
コードは雄弁。でも、文脈はしゃべってくれない
プログラムは正しく動けばそれでいい──
そう思いがちですが、第三者から見れば、
「なぜこういう構造になっているのか?」
「どんなユースケースを想定しているのか?」
「自分の環境でも動かせるのか?」
…など、“コードの外側”の情報がないと、使うのも学ぶのもハードルが高く感じられます。
たとえばあなたが誰かのリポジトリを見に行って、READMEが何もなかったらどう思いますか?
「とりあえずクローンして中身読めばいいのかな…いや、やめとこ」ってなる人、多いと思います。私もそうでした。
README=履歴書 × ランディングページ
READMEは、ざっくり言えば「あなたのプロジェクトの履歴書」であり「ランディングページ」でもあります。
最初に見られる場所であり、「このプロジェクトを使ってみたい!」と思ってもらえるかどうかの分かれ道。
特に転職活動中のエンジニアや、技術ブログでコードを公開している人にとっては、 「READMEの出来=第一印象」になることすらあります。
READMEは、過去の自分と未来の誰かを助けてくれる
READMEのメリットは、他の人だけでなく自分自身にもあるという点です。
半年後に「あのコード、どうやって使うんだっけ…」と過去の自分のリポジトリを開いたとき、READMEが整っていればめちゃくちゃありがたいですよ。
さらに、READMEがあることで、未来のあなたのブログ読者、後輩、あるいはGitHubで出会う誰かが、そのコードを安心して使える・学べるようになります。
結論:「READMEを書くこと」は、やさしさであり、技術力でもある
READMEは、「きちんと伝えようとする姿勢」がにじみ出る場所です。
それはつまり、“人のことを考えられるエンジニア”という印象につながるんですね。
だからこそ、READMEはただの“おまけ”ではなく、 あなたのスキルとやさしさを同時に伝えてくれる、立派な技術資料なんです。
Markdownとは?READMEでよく使う記法をざっくり解説
READMEを書くとなると、まずぶち当たるのが「Markdownって何?」問題。
私も最初は「マークダウン?なんかRPGの呪文みたい…」と思っていました。
でもご安心を。Markdownは、“かんたんな記号で文章に装飾を加えるルール”のこと。
見出しをつけたり、コードを整えたり、リンクを貼ったりするための「シンプルな言語」なんです。
Markdownでできること(=READMEが劇的に見やすくなる)
HTMLのように複雑なタグを使うことなく、直感的に構造を整えられるのがMarkdownの魅力。
GitHub上では自動でMarkdownがレンダリングされ、見やすいレイアウトに変換されます。
具体的に、こんなことができます:
| やりたいこと | 書き方 | 表示例 |
|---|---|---|
| 見出し | # 見出し1、## 見出し2 | 見出しが大きくなる |
| リスト(箇条書き) | – 項目1、* 項目2 | 箇条書きになる |
| リンク | [グーグル](https://www.google.com/?hl=ja) | クリックできる文字に |
| コードブロック | \\で囲む or インラインは \text` | コードとして表示される |
| 強調 | **太字**、*イタリック* | 強調される |
| 表 | | TH | TH | | —- | —- | | TD | TD | | TD | TD | | 表が作れる |
覚える必要があるのはたったこれだけ。 いきなり全部使いこなせなくても大丈夫。READMEを書く中で、自然に身についていきます!
Markdownの学び方:「いじって覚える」が正解
「記法を完璧に覚えてから書こう」と思うと挫折します。
おすすめは、「ひとまず書いて → GitHubで表示 → 見た目を調整」の繰り返し。
GitHubのREADMEはコミットごとに更新履歴が残るので、試行錯誤しながら“育てていく資料”にしてOKなんです。
そして何より、見出しやリストを使うだけでグッと見やすくなるのを体感できると、Markdownって楽しくなってきますよ
とくにREADMEでよく使う3つの構文
迷ったら、この3つだけ覚えておけば十分スタートラインに立てます💡
- 見出し(#) → # プロジェクトの概要 で、章ごとに区切る
- リスト(-) → 使い方や特徴などを箇条書きで整理
- コードブロック(\\\`) → サンプルコードをきれいに表示できる(VBA, SQL などにも◎)
これだけで「読まれるREADME」にグッと近づきます!
Markdownは、コードを書く人の“やさしい文法”
Markdownを覚えるのは、「文章を整える」ためではなく、「読む人のことを考えた情報の伝え方」のひとつです。
そしてそれは、「共感」と「実用性」にもつながっています。
次章では、Markdownでどんな項目を書けば“伝わるREADME”になるのか、そのテンプレートを一緒に見ていきましょう!
“伝わる”READMEを書くための構成テンプレート
Markdownが少しずつ使えるようになってきたら、次に考えるのは「何を書けばいいの?」問題。
READMEに正解はありませんが、読まれる・使われるREADMEには、共通して“伝えるべき項目”があります。
この章では、そんな「伝わるREADME」を書くための基本テンプレートと、それぞれの項目に何を書けば良いのかを具体的にご紹介します。
READMEの基本構成テンプレート
# プロジェクト名
## 概要(What)
このプロジェクトが何をするものか、ひとことで。
## 背景(Why)
なぜこれを作ったのか。どんな課題を解決したかったのか。
## 使い方(How)
インストール方法や実行方法など、再現できる手順を。
## 前提条件 / 実行環境
使用した言語、フレームワーク、バージョンなどを記載。
## スクリーンショット(任意)
動作画面や出力結果の画像を貼ってイメージを伝える。
## 補足・注意点(任意)
使い方のコツや、注意事項など。
## ライセンス
MIT など、ソースコードの利用条件を書く。
## 作者 / リンク(任意)
誰が作ったのか、ブログやSNSなどのリンクがあると親しみUP。このように、「What / Why / How」を意識して構成するだけでも、読者から見た理解度がぐんと上がります。
各セクションを“伝わる文章”にするコツ
| セクション | 書くと良いことのヒント |
|---|---|
| 概要 | 一文でOK。「〇〇を自動化するツールです」「業務用に作ったVBAマクロ集です」など端的に。 |
| 背景 | 「手作業が面倒だった」「同じエラーに3回悩んだから作った」など個人的な動機も好感度UP。 |
| 使い方 | 実行コマンドや手順を numbered list で丁寧に。失敗しやすいポイントも添えると親切。 |
| 環境 | OS、言語、バージョンを明記。「動かない…」トラブルを防げます。 |
| スクリーンショット | Before / After 画像やGIFがあると、イメージが一気に湧きます。 |
| 補足 / 注意点 | 特定の入力形式・制約条件など。「〇〇をしないと動きません」などの一言でトラブルを回避。 |
READMEテンプレ例:シンプルなツールの場合
# Excel日報自動作成マクロ
## 概要
毎日のExcel日報をボタン1つで作成できるVBAマクロです。
## 背景
手書きで同じフォーマットを毎日コピペするのが面倒すぎたので作りました。
## 使い方
1. このリポジトリをクローン or ZIPでダウンロード
2. `nippou_macro.xlsm` を開く
3. 「日報作成」ボタンを押すだけ!
## 動作環境
- Windows 10
- Excel 2016 以上
## 補足
- 記入テンプレートの配置場所は `config/config.xlsx` で設定できます。
## ライセンス
MIT Licenseどうですか?難しい言葉や形式にこだわらなくても、「何を」「なぜ」「どう使う」をきちんと伝えるだけで、“優しいREADME”になりますよね。
まとめ:READMEは「説明書」ではなく「手渡しメッセージ」
テンプレートを使うのは、形式を整えるためだけじゃありません。
「このコードは、こういう思いで作ったんだよ」と伝える“設計図付きのラブレター”のようなものです。
次章では、逆に「これは避けたい!」というNG例や読みやすさのチェックポイントを紹介します。
伝わるREADMEを育てるためのヒント、まだまだありますよ。
ありがち失敗あるある&読みやすさチェックリスト
せっかく時間をかけてREADMEを書いたのに、「あれ…なんか読みにくい」「何が書いてあるか分からない」と思われてしまったら、ちょっと悲しいですよね。
この章では、初心者が陥りやすい失敗例と、それを防ぐための“読みやすさセルフチェックリスト”をご紹介します。
先に知っておくだけでグッと仕上がりが変わってくるので、ぜひ参考にしてください!
ありがちNG READMEあるある
| 失敗パターン | なにが起きてるか | 改善のヒント |
|---|---|---|
| READMEが空っぽ(コメントアウトのみ) | 見に来た人が「え、なんのプロジェクト…?」と混乱 | 最低でも「概要+使い方」だけは書いておこう |
| 説明ゼロでコードだけドーン! | 「読んで理解しろ」という圧がすごい | Markdownで見出しと手順を付けてあげるだけで親切に |
| 長すぎて途中で読む気が失せる | 小説級のREADME。まるで説明書に負けたRPG | セクションで分けて見出しを付けよう。折りたためる章構成が◎ |
| 専門用語だらけで初心者お断り感 | 難しい言葉に囲まれて“README格差社会”を感じる | 用語には軽く補足を。書いた本人だけが理解できる文は卒業! |
| Markdownが崩れて表示がぐちゃぐちゃ | 表やコードがズレて読みにくい | プレビュー機能で表示確認!1行空けるだけでも見やすさアップ |
こういう「惜しいREADME」は、ほんの一工夫で“読まれたくなるREADME”に生まれ変わります。
読みやすさセルフチェックリスト
READMEを書いたあとに、以下のチェック項目を確認してみましょう:
- [ ] プロジェクトの目的が一文で伝わる
- [ ] 使い方の手順が3ステップ以内で書かれている(または見やすく分割されている)
- [ ] コードブロックやスクリーンショットで具体的な操作がイメージできる
- [ ] 専門用語を使っている箇所には軽く補足がある
- [ ] 見出しやリストで内容が整理されている(だらっと長文になっていない)
- [ ] Markdownの表示崩れがない(プレビューで確認済み)
- [ ] ライセンスや注意書きなど最低限のフッター情報もある
- [ ] 「これを書いたのは誰?」がわかる(作者情報やブログ・Xのリンクなど)
このチェックリストにすべて◯がつけば、あなたのREADMEは「読まれる技術資料」としてバッチリ機能しているはずです!
伝える気持ちのあるREADMEは、ちゃんと伝わる
間違いや失敗があったって大丈夫。大事なのは、「読む人のことを考えて書こう」と思えるかどうかです。
Markdownの記法よりも、その奥にある“伝える姿勢”が、READMEの読みやすさを決めてくれます。
次の章では、そんなREADMEがより広く活かせるように、GitHubならではの活用法とちょっとした+αの工夫をご紹介していきますね
READMEで差がつく!GitHubだからこそできる工夫
基本的なREADMEを書けるようになったら、あとはコードを置いておくだけ…と思いがちですが、ちょっとした工夫で「魅せるREADME」に進化させることができるのがGitHubの面白いところです。
この章では、GitHubだからこそできる+αの表現や見せ方、連携アイデアをご紹介します!
バッジ(Shields.io)で「見た目にも楽しく」
READMEの冒頭でよく見かけるこんなカラフルなやつ、見たことありませんか?
→
これは Shields.io というサービスで簡単に作れるバッジです。
プロジェクトのライセンスや使用言語、最終更新日、ビルド状況などを“ステータスっぽく”表現できます。
ちょっと遊び心があるだけで、ぐっとプロジェクトに活気が出るんですよね。
GitHub PagesでドキュメントをWebサイト化
READMEだけだと情報がまとまらないと感じたら、docs/ フォルダや GitHub Pages を活用しましょう。
Markdownで書いた複数の技術資料を、Webページのように見せることができます。
- チュートリアル形式にしたい
- APIドキュメントなどをまとめたい
- ちょっとスタイリッシュに見せたい
というときに便利です!
Wiki機能で多ページ構成の技術ドキュメントに
GitHubリポジトリには、Wikiページを作成できる機能があります。
複数ページに分けて手順書やガイドを書けるので、READMEが長くなりすぎる場合にもおすすめです。
Markdownで書けるので学習コストも低く、ちょっとした「プロジェクト内ナレッジベース」として使うことも可能です。
他メディアとの連携で“発信力”を強化!
技術ブログを運営しているなら、READMEにその記事のリンクを貼るのも◎。
さらに、以下のような使い方もできます:
- Qiita・Zenn・noteの記事とGitHubを相互リンク
- SNSで紹介するときにREADMEのキャッチコピーを添える
- READMEの一部に「作成者ノート」を添えて、ブログに誘導!
発信と資料のハブにREADMEを使うという視点で考えると、技術ブログとの相乗効果がどんどん広がっていきます。
あなたのREADMEに「らしさ」を宿す工夫
読んだときに「おっ」と思ってもらえるREADMEには、その人らしさがにじみ出ています。たとえば:
- タイトルに絵文字や一言ユーモア
- 背景に「この課題にハマって寝れなかった」などの実話を添える
- コメントに“未来の自分へのメッセージ”っぽい言葉を入れる
こうした小さな個性の演出が、あなただけのREADMEを作るスパイスになります。
まとめ:READMEは「伝える」から「届ける」へ
GitHubのREADMEは、コードを補う説明書ではなく、読む人の背中を押す“技術の案内板”のようなもの。
Markdownで書かれたその文章に、ほんの少し工夫を加えるだけで、コードの価値もあなたの伝えたい想いも、ちゃんと届くようになります。
次章では、今回の内容をふまえて、記事全体のまとめと「最初の一歩を踏み出す勇気」についてお届けします。
まとめと、最初のREADMEを書いてみよう
ここまで読んでくださったあなた、まずはお疲れさまでした。
READMEという言葉すら「なんか空のファイルあるな?」くらいだった私が、今こうしてMarkdownを使って記事を書いてるわけです。
つまり、「最初は分からなくても、やってみればなんとかなる」というのは、本当なんです。
READMEは、あなたの技術を言葉にする場所
READMEは単なる説明書ではなく、
- コードの背景を語れる場所
- 未来のあなた(と誰か)を助ける場所
- あなたらしさがにじむ技術資料
なんです。
特別な言葉なんて必要ありません。今のあなたの言葉で、精一杯書いてみることが、なにより伝わります。
今からできる、小さな一歩
記事を読んだあとに、今日できることを1つ挙げるとすれば――
それは、「自分のリポジトリにREADME.mdを追加すること」です。
中身が未完成でもOK。
とりあえず「これは〇〇用のツールです」と一文書いて、コミットしてみてください。
その一歩が、明日の自分を助けてくれたり、誰かからの「ありがとう」を生むかもしれません。
書くことで、見えてくるものがある
READMEを書くことで、自分の思考が整理され、「自分、ここまで学んできたんだ」と再確認できます。
そして、ほんの少しMarkdownやGitHubが楽しくなってきたら――
それはもう、あなた自身が“技術を伝える人”になり始めているということ。
最後に
完璧じゃなくていい。丁寧でなくてもいい。
でも、「伝えたい」という気持ちを、READMEに込めてみませんか?
あなたのコードに、あなたの言葉を。 その記録が、誰かの役に立ち、あなた自身の自信に変わっていくはずです。
一緒に、今日、最初のREADMEを書いてみましょう!

「READMEを書いてみようかな」「Markdownって意外と楽しいかも」と、ほんの少しでも思っていただけたなら、この記事を書いた意味はあったなぁと思っています。
私は、コマンドにビビってGitHubから逃げ出したことも、READMEを空のまま放置していたこともあります。 でも、ほんの一文でも「伝えよう」と思ってREADMEを書いてみたら、不思議と気持ちが整理されて、少しだけ自信が持てるようになりました。
コードを書く手は未来へ向かっているけれど、READMEは過去の自分や、これから出会う誰かとつながる道しるべ。 あなたの技術と想いが、READMEという形で誰かに届く日がきっと来ます。
どうか、最初の一歩をおそれず、あなたの言葉でREADMEを書いてみてください。 一緒に、やさしくて伝わる技術の記録を育てていきましょう!
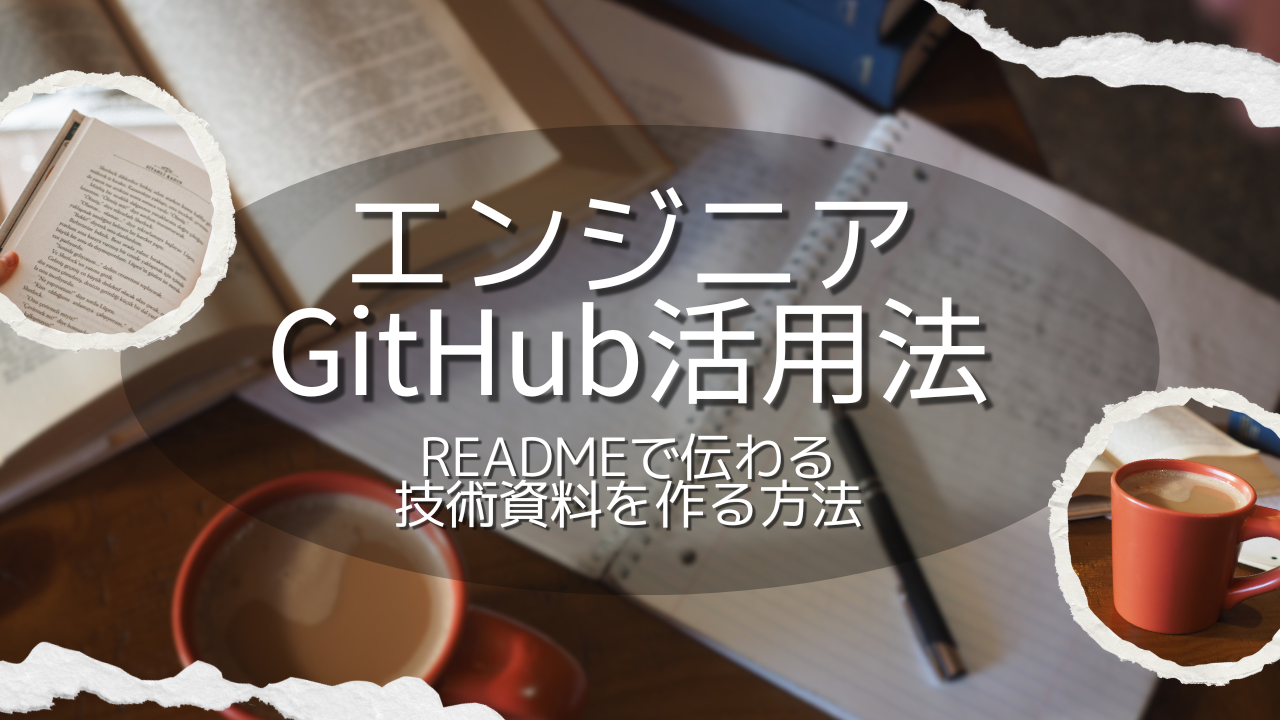
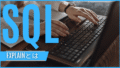
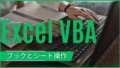
コメント