「資格って、意味ないと思うよ。」
ある日、上司にそう言われたとき、私は頭の中が一瞬フリーズしました。
ちょうど資格の勉強をしていたタイミングだったので、「え、それって私の努力を否定してる…?」と心の中でざわついたのを今でも覚えています。
せっかく前向きに学ぼうとしていたのに、その意欲に水を差されたようで、とてもショックでした。
IT業界では、「資格より実務経験が大事」といった声をよく聞きます。
いわゆる「資格不要論」です。
でも、初心者エンジニアにとっては、本当にそうなのでしょうか?
この記事では、私が資格の価値に悩んだ体験をもとに、「資格不要論」にどう向き合えばいいのか、そして資格がキャリアやスキルアップにどう役立つのかを整理していきます。
資格を取るべきかどうか迷っている方のヒントになれば嬉しいです。
資格は意味ないってホント?「資格不要論」に触れた瞬間
資格の勉強を始めた頃のことを思い出すと、今でも少し複雑な気持ちになります。
当時、私はエンジニアとしてのキャリアを始めたばかりで、技術的な知識を一つひとつ丁寧に積み上げようとしていました。
その一歩として選んだのが「資格を取る」という選択。
知識を体系的に学べること、そして自信にもつながることを期待して、前向きな気持ちで勉強を進めていたんです。
そんなある日、職場の上司との何気ない会話の中で、こんな言葉を投げかけられました。
「資格?意味ないよ。実務ができなきゃ評価されないから。」
一瞬、頭の中が真っ白になりました。
「え、じゃあ私が今頑張っていることって、無駄なの…?」 言葉にできないショックが、じわっと胸に広がったのを覚えています。
たしかに、IT業界ではよく「資格より実務経験が大事」「資格は所詮、紙切れ」といった意見を耳にします。
その考え自体を否定するつもりはありませんし、現場でのスキルが大切なのは間違いないと私も感じています。
でも、「だから資格は意味がない」という極端な言い切りには、どこかひっかかりを覚えました。
私にとって資格取得は、ただの肩書きではありませんでした。
知らなかったことを学び直すきっかけでもあり、自分の理解を“見える形”で確認する手段でもありました。
誰かの評価のためではなく、「自分のペースで成長していきたい」という気持ちから始めたこと。
それを、あっさり否定された気がして、心のどこかがざわついたのです。
でも、この出来事がきっかけで、私はあらためて考えるようになりました。
「資格って本当に無意味なのか?」「実務と資格、どちらを優先すべきなのか?」 迷いながらも、自分なりの答えを探すことが、エンジニアとしての“軸”を作る第一歩になったと思っています。
なぜ「資格より実務」と言われるのか?—資格不要論の正体
IT業界にいると、よく耳にするのが「資格より実務経験が大事」という言葉です。
実際、現場の求人票を見ても、「〇〇資格必須」といった表現よりも、「〇年以上の開発経験」や「特定の技術スタックに関する知識・実績」が優先されていることが多い印象を受けます。
このような風潮が、いわゆる「資格不要論」と呼ばれる考え方につながっています。
「資格があっても実務ができなければ意味がない」
「資格取得よりも現場で手を動かした方が早い」
——こうした意見が広まっているのには、いくつかの背景があります。
まず、IT業界は変化のスピードが非常に速いため、資格試験の内容が現場の技術トレンドとズレてしまうことがあります。
特に新しいフレームワークやクラウド関連の分野では、実務で得る最新の知識こそが最も役立つ、という実感があるのも事実です。
また、現場では「アウトプット」が重視される傾向もあります。
資格はあくまで「インプット」の証明であり、開発経験やGitHubのポートフォリオといった実績の方が、採用担当者にとっては具体的な評価材料になりやすいのです。
特に中途採用やフリーランスなどでは、「実務で何ができるか」が重視されるため、資格は二の次にされがちです。
たしかに、これらの考え方には合理的な面があります。
この記事を読んでくださっている方も、現場で経験を積んでいく中で「資格がなくても成果を出せる人はたくさんいる」と実感されてきたのではないでしょうか。
でも、だからといって「資格=無意味」とまで言い切ってしまうのは、少し極端かもしれません。
資格が本来持つ価値、たとえば、学びの指針になることや、土台を築くためのステップであることは、実務経験が少ないエンジニアほど大きな意味を持つはずです。
この章では、あえて「資格不要論」の視点に立ってみることで、その主張の背景と盲点を整理してみました。
資格は初心者の武器になる!キャリアに役立つ3つの力
資格なんて意味がない
――そんな言葉を聞いて戸惑った私でしたが、それでも「やっぱり勉強してよかった」と思える理由が、いくつもあります。
実際に資格の勉強を進めていく中で、「ああ、自分にはまだ知らないことがたくさんあるな」「こういう仕組みだったのか」と新しい発見があったり、理解できることが少しずつ増えていったりする感覚がありました。
これは、私にとってすごく大きなモチベーションになりました。
特に、これからエンジニアとしての基礎を築いていこうとする初心者の段階では、資格は次のような「3つの力」をくれると感じています。
知識を体系的に学べる「整理の力」
エンジニアの世界では、情報の量もスピードも膨大です。
独学であれこれ調べていると、何から学ぶべきか迷ってしまったり、知識がバラバラになって頭に残らなかったりすることもあります。
資格試験の教材や出題範囲は、そうした知識を体系的に整理してくれる“地図”のような役割を果たします。
「自分は今、こういう分野を学んでいるんだ」「この概念とあの技術はつながっているんだ」と気づけたとき、学びがぐっと深まった気がしました。
「まだ実績がない」自分を支えてくれる信頼の足がかり
実務経験がない、もしくは少ない段階では、自分のスキルをうまく証明するのが難しいと感じることがあります。
そんなとき、資格は“これだけの内容を学び、理解しました”という目に見える証として役立ちます。
もちろん、資格を持っているだけで採用されるわけではありませんが、面接やプロフィールの中で「どんなことを意識して学んできたか」を伝える材料になるのは間違いありません。
特に未経験からの転職や、キャリアのスタートラインに立っている人にとっては、ひとつの自信にもつながります。
自分に足りないものに気づける「視野を広げる力」
資格の勉強をしていると、「これまで気にしていなかった技術」や「現場では当たり前だけど曖昧にしていた知識」に出会うことがあります。
たとえばネットワークの基本や、情報セキュリティの考え方など、実務では意外と“知っている前提”で進んでしまうテーマにも、資格学習を通じて向き合うことができました。
こうした「技術の視野を広げる力」は、実際の業務やチームでの会話でも大きく役立ちます。
学びを深める中で、「これをもっと知りたい」「ここを強化したい」という気持ちも自然と芽生えてくるので、資格はまさに“今後どう成長していきたいか”を考えるきっかけにもなるのです。
資格を活かすには?初心者エンジニアが取るべき戦略的ステップ
資格を取ることはゴールではありません。
むしろ、そこからが本当のスタートだと私は思います。
せっかく時間をかけて勉強し、知識を身につけたのなら、それをどうキャリアや実務につなげていくかを考えることがとても大切です。
私自身、「資格取得=即戦力」ではないことを痛感したことがあります。
合格通知を手にして達成感はありましたが、それだけでは現場では何もできなかったからです。
だからこそ、資格を“意味あるもの”に変えていくためには、次のようなステップを意識するようになりました。
ステップ1:目的を明確にして資格を選ぶ
まず、「何のために資格を取りたいのか?」をきちんと自分に問いかけることから始めてみましょう。
- 転職でアピールしたいから
- 学習のペースを整えたいから
- 苦手分野を克服したいから
目的が明確になると、選ぶべき資格の種類や勉強法も変わってきます。
たとえば、「とにかく基礎を固めたい」なら ITパスポートや基本情報技術者試験、「インフラに興味がある」なら Azure や AWS の入門資格、といった具合に、自分のキャリアと紐づいた選択ができます。
ステップ2:実務とのつながりを意識する
資格の知識をインプットしたら、できるだけ早いタイミングで「実務に落とし込む感覚」を持つことが重要です。
私の場合、Javaの資格に興味を持ったとき、「あ、でも実務ではどんなふうに扱われてるんだろう?」という視点が抜けていたことに気づきました。
そこで、実際のプロジェクトでJavaを使うチャンスがあれば積極的に関わるようにして、学びと実践がリンクしていく感覚をつかみました。
これはまさに「資格の中身にリアリティを与える」作業だと思っています。
座学の知識を、手を動かしながら少しずつ“自分のスキル”として染み込ませていくような感覚です。
ステップ3:発信して“学びを共有資産”にする
意外かもしれませんが、「学んだことをブログやSNSで発信する」ことも資格を活かすうえでとても有効です。
学びのアウトプットは、自分の理解を深めるだけでなく、周囲からの信頼や共感にもつながります。
資格勉強の過程で「ここが難しかった」「こうやって覚えた」などの気づきは、これから同じ道を歩む人にとって貴重な情報になります。
実際、私自身も何度も他の方の発信に励まされましたし、自分も誰かの役に立てたらいいなという気持ちで、少しずつ記事を書き始めました。
発信することで「学びが成果になる」という実感が得られるので、資格の価値がより実感できるようになります。
ステップ4:「資格×スキル」のバランスを整える
最後に伝えたいのは、「資格を取ったから安心」という状態にならないようにすることです。
資格は“強力な道しるべ”ですが、それがあるだけでキャリアが自動的に広がるわけではありません。
だからこそ、私は資格を「スキルや実務と組み合わせて使うもの」だと考えています。
たとえば、資格で得た知識を活かしてちょっとしたツールを自作してみる、実際の案件で部分的に担当してみる、ブログで噛み砕いて発信する……
そんな小さな積み重ねが、「資格を活かす」という行動につながっていくのだと思います。
まとめ—資格に振り回されず、自分のキャリア軸で選ぼう
「資格は意味がない」「資格を取っても現場では通用しない」
——そんな声を聞いて、迷いや不安を感じた方も多いのではないでしょうか。
私もそうでした。せっかく前向きに勉強していたのに、水を差されたような気がして、立ち止まってしまったこともあります。
けれど、その経験を通じて私は気づきました。大切なのは、“資格が必要かどうか”ではなく、“自分にとってそれが必要かどうか”という問いです。
資格はそれ自体がキャリアを築いてくれるわけではありません。
でも、学びの指針になったり、自信につながったり、自分の可能性を広げてくれる存在でもあります。
他人の価値観ではなく、自分の目線で選ぶ。そのうえで、資格をどう活かすかを考えていく
——それが本当の意味で「資格を意味あるものにする」方法だと思うのです。
資格不要論に振り回される必要はありません。
むしろ、そうした声を客観的に見つめたうえで、自分の意思で判断する力こそが、これからエンジニアとして生きていくうえで一番大切なのではないでしょうか。
これから資格取得を考えている方にとって、この記事が少しでも判断のヒントになれば嬉しいです。
迷いながらも前に進もうとしている姿勢自体が、すでに立派な成長への一歩です!
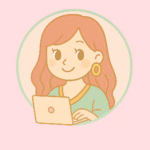
私自身、迷いながらも勉強を進め、悩みながらも小さな一歩を重ねてきました。そして今もまだ、その途中にいます。この記事が、誰かの「ちょっと前に進んでみようかな」という気持ちにつながっていたら嬉しいです。
どんな選択も、きっとあなたのキャリアの糧になるはずです。焦らず、自分のペースで、一緒に頑張っていきましょう!
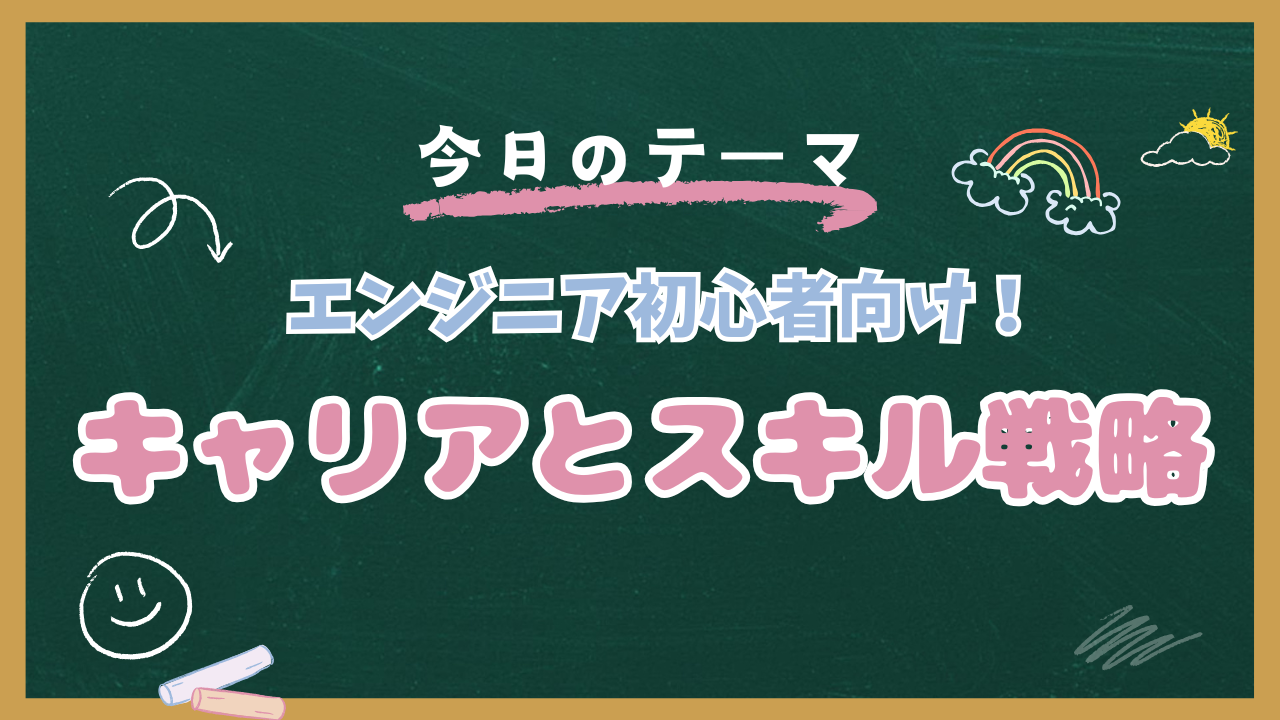
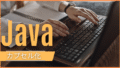

コメント