「えっ、私が教える側…ですか?」
SQLを学ぶのに必死だったあの頃。
SELECT文を書いて、動いた!返ってきた!よっしゃー!とガッツポーズを決めていたあの頃。
そんな自分がある日、未経験の方にSQLを教えることになりました。
「えっ、教えるって…私が⁉︎」 「いや待って、私、自分が分かってる風になってるだけじゃない…⁉︎」 「この説明、伝わってるのか…?(謎の脇汗)」
そんな焦りと戸惑いがごちゃ混ぜになって、 自信よりも不安が100%だった教え始めの私がいました。
この記事は、そんな「教える側、ちょっとこわい…」という方に向けて書いています。
- そもそもSQLって、どう説明すれば伝わるの?
- 初心者さんがつまずくポイントってどこ?
- 自分の説明、何が良くて何がモヤッとしたのか振り返りたい…
そんな思いを持つあなたに、「説明の上手い先輩になるためのヒント」を、 実際の失敗談や試行錯誤も交えながらお届けできたらと思います。
自分も学びながら、教えることで気づくことがたくさんあるはずです。 一緒に“伝え方”のスキルを育てていきましょう!
「SQLを教える」って、なんでこんなに難しいんだろう?
SQLの書き方をなんとなく覚えて、 少しずつJOINやGROUP BYにも慣れてきて、 「おっ、私、ちゃんとSQLわかってきたかも」と思い始めたころ。
ある日、ふいに訪れた“教える機会”。
「この新人さん、SQL初めてみたいだから、軽く教えてあげてくれる?」
……そのときの私の心の声
- え、教えるってどうやるの…?
- 自分の理解って、ほんとに人に説明できるほどあるの?
- ていうかGROUP BYってなんで必要なんだっけ…?
それまで使えていたはずの構文たちが、 “誰かに説明する”という瞬間に一気に自信喪失させてくるのです。
「分かる」と「説明できる」は別物だった
実際にやってみて気づいたのは、 頭では分かっていたつもりのことほど、言葉にしようとすると曖昧になるということ。
- 自分はなぜINNER JOINを使ったのか?
- どうしてWHEREじゃなくてHAVINGなのか?
- NULLって“空っぽ”って説明すればいいのかな…?
初心者さんからの素直な質問ほど、核心を突いてくるものです。 そしてそのたびに、「あれ?私、説明できないぞ…」と焦る。
自信がないのは、ちゃんと考えようとしてる証拠
でも今なら思います。 あのときの「ちゃんと説明できない」という不安は、 “相手にちゃんと伝わるように届けたい”という、誠実な姿勢の裏返しだったんだと。
だからこそ、この記事の最初の章ではお伝えしたいのです。
- 教えるときに不安になったって大丈夫です
- 完璧な知識よりも、伝えようとする工夫のほうがずっと大切です
- 伝えようとすることで、理解はむしろ深まっていきます
この章は「教える=知識の高さ」ではなく、 「教える=相手に寄り添う姿勢」だというメッセージを届ける場でもあります。
次の章では、そんな“教えられる側”がどこでつまずきやすいのか、 初心者目線から紐解いていきます。
初心者にありがちな“わからないサイン”と誤解の芽
「SQLを教えてみて気づいたのですが…」と、多くの人が口にするのが、 「初心者の“分からない”が想像以上に分からない」ということ。
経験者にとって“なんとなく当たり前”に感じていたことほど、 初心者にとっては「???」の宝庫だったりします。
「SELECTは分かるけどJOINは無理」現象
最初の壁、それがJOINです。
SELECT * FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id;このたった1文が「異世界召喚句」に見える人、多いです。
- 「テーブルをくっつけるって、どういうこと?」
- 「片方のテーブルにない情報が混じってくるのが意味不明」
- 「JOINすると行数が増えるのなんで?」
教える側は「IDが一致してるだけだよ」とサラッと言いがちですが、 “IDでつなぐ”という行為自体がピンときていない可能性もあります。
「GROUP BYが呪文に見える」問題
SELECT user_id, COUNT(*) FROM orders GROUP BY user_id;この1文。初学者にとっては以下の反応を引き出すことがあります:
- 「GROUPって“並び替え”じゃないの?」
- 「SELECTに書いたカラム、全部GROUP BYに入れないとエラーになる謎ルール怖い」
- 「集計されるのに、行は複数返ってくるのが混乱する」
特に、「何をグルーピングしているのか」がイメージできないと “書けるけど意味が分からない状態”になってしまいます。
順番通りに書いてるのに「順番通りに処理されない」混乱
SQLは、書き方と実行順序が違うという“直感とのギャップ”がある言語です。
SELECT name FROM users WHERE age > 20 ORDER BY created_at;このような文も、実際には
- FROM(どのテーブルを対象にするか)
- WHERE(条件で絞る)
- SELECT(カラムを取り出す)
- ORDER BY(並び替える)
という裏の流れで処理されます。
でも初心者にとっては、「SELECTが最初に書いてあるのに最初じゃないの?」という “構文と動作のズレ”が混乱の原因になるのです。
「NULLってゼロ?空白?何もしないもの?」疑惑
NULLに出会った初心者は、9割方混乱します。
- 「= NULL で比較するとマッチしないのなんで?」
- 「COUNT(*) すると入ってくるけど、COUNT(column) だと除外されるの、地味にハマる」
- 「NULL = NULL がFALSEって、哲学かな?」
実はこの辺りこそ、教える側が“分かった風”になりがちな難所。
うまく伝えるためには、初心者の混乱ポイントを一歩引いて眺める視点が必要です。
まとめ:「つまずく理由」は構文の前に“思考の前提の違い”かも
初心者がつまずく原因は、決して“理解力が低い”からではありません。 むしろ「経験者と“見えている地図”が違う」だけなんです。
- データとは何か?
- なぜ複数テーブルに分けるのか?
- どうやって“探して”“整えて”“返す”のか?
これらの当たり前にしていたことの言語化が、 伝わる説明への第一歩になるはずです。
次章では、こうしたギャップを埋めるどころか広げてしまいがちな「教えるときのNGパターン」を、反面教師として紹介していきます。
「やっちゃってたかも…」という小さな気づきが、“伝え方の改善”の種になりますよ!
教えるときによくあるNGパターンとその理由
「ちゃんと説明したのに、なんで伝わらないんだろう?」 教える経験を重ねる中で、私が最初にぶつかった壁でした。
でも、あとから思い返すと──
自分がやっていた“伝わらない理由の種”は、ちゃんと撒かれていたんです…
この章では、私自身の反省も込めて「ついやってしまいがちだけど、初心者には伝わらないかもしれない説明のクセ」をご紹介します!
NG①:「この構文を暗記しておけば大丈夫」方式
SELECT col FROM table WHERE 条件;「この形で覚えればOKだよ〜」とテンプレ的に教えてしまったこと、ありませんか?
なぜNGか?
- 暗記では“応用”が効きません(別のカラム名・別の目的に対応できない)
- 初心者さんの頭の中:「何のためにこの形なのかがわからない…」
- 結果として「“呪文”を毎回コピペしているだけ」になりがち
対処のヒント
- 「これは“何を選んで、どこから、どんな条件で”を伝える構文なんだよ」と動詞ベースの解釈にしてあげると理解しやすくなります!
NG②:内部処理や最適化の話を突然出す
私:「このJOINは内部的にはハッシュ結合なんだけど〜」
初心者:「ハ…ハッシュ…?なんか急にプログラミング言語っぽくなった…!」
なぜNGか?
- まだ目の前の構文すら理解しきれていない段階では、「裏側の最適化」の話は頭に入りきりません
- 話のギアが5段階くらい急に上がると、聞き手は“置いてけぼり感”を強く感じます
対処のヒント
- 「まずは動く例」から → 慣れてきたら「実行計画や工夫もあるよ」と段階的に話す
- “関心を持てたタイミング”が一番学びやすいというのを大切に!
NG③:「知ってる前提」で始めてしまう
私:「ここでキーをJOINして、WHERE句で絞って〜」
初心者:「キーって何?JOINって何?WHEREって何?(全部わからん)」
なぜNGか?
- 経験者にとって常識になっている言葉ほど、初心者にとっては“専門用語の塊”です
- 知らない単語が1文に3つ以上出ると、読解以前に脳が拒否反応を起こします
対処のヒント
- 「知ってるだろう」でなく、「初めて聞くかもしれない」を前提に話す
- “単語の説明から始める”ことは甘やかしではなく、やさしさです。
NG④:「SELECT 社員名 FROM 社員」ばかりの例文
いかにも教材に出てきそうなやつですね。
なぜNGか?
- 現実の業務には「社員」より「注文」「商品」「ユーザー行動」など複雑なデータ構造が多く、実務とのギャップが大きい
- 初心者は「こういう簡単な例にしかSQLって使えないのかな…?」と逆に誤解してしまうことも
対処のヒント
- 少しだけリアリティのある例(ECサイト、SNS、レポート系など)に置き換えてみる
- 「このクエリは“ログを集計して分析する”みたいなイメージだよ」と使う場面もセットで伝える
小まとめ:「伝わらない」は“説明力不足”ではなく“構造ギャップ”
伝わらない説明って、実は“相手と見ている景色が違う”ことに気づかないことが原因だったりします。
- 自分の説明が難しすぎたのかも? → ✕ 前提を飛ばして話し始めていた
- 相手が理解力ないのかも? → ✕ こちらが例を用意できていなかっただけかも
そんな風に、“伝わらない”の責任を100%自分に背負わせるのではなく、 「仕組みを整えたら、もっと伝わるんじゃない?」と考え直せると、グッと楽になりますよ◎
次の章では、そんな「伝わりづらい」を解消するために私が試して効果があった“3つの工夫”を、言葉選びや比喩の具体例とともにお伝えします!
説明がちょっと楽しくなってくるかもしれませんよ!
“伝わるSQLの教え方”に必要な3つの工夫
初心者に何かを伝えるとき、「どう言えば伝わるかな?」と考えることって、 実はそのまま“相手へのやさしさ”なんだと思います。
この章では、私がいろんな試行錯誤の中で「これは伝わった!」と思えた工夫を3つご紹介します。
工夫①:比喩とイメージで理解のハードルを下げる
SQLの構文や概念は、抽象的でとっつきにくいものが多いですよね。
そんなときに効果的なのが、日常生活や身近な物ごとにたとえる工夫です。
たとえば:
- JOINは“名簿と成績表を照合する”作業:「同じ番号を持つ人同士を突き合わせてるんだよ」
- GROUP BYは“業務ごとにホチキス止めする”イメージ:「同じ担当者ごとに束ねて、件数や合計金額を出す感覚」
- NULLは“情報がまだ書き込まれていない白紙の欄”
「あっ、なんか分かる気がする!」を生む一言こそ、最強の橋渡しツール!
工夫②:構文の“見た目”ではなく“処理の流れ”から説明する
SQLは、書き方よりも「処理の順番」で理解するほうが納得感が生まれやすい言語です。
初心者にとっては…
SELECT name FROM users WHERE age > 20 ORDER BY created_at;と書いてあるのに、「SELECTが最後に実行されるって何!?」とパニックになりがち。
だからこそ、以下のように読み方の順番を先に教えるのがおすすめです:
▼ 実際の処理の流れ
- FROM(どのテーブルを見るか)
- WHERE(どれを対象にするか)
- GROUP BY(必要ならグループ化)
- SELECT(何を取り出すか)
- ORDER BY(並び替える)
“読む順番=実行の順番”と意識できるようになると、構文の意味もスーッと入ってきます!
工夫③:相手と一緒に「手を動かしながら気づく」説明にする
初心者にとって、話を聞くだけより、“手を動かして結果を見た瞬間”のほうが圧倒的に理解が深まります。
たとえば:
「このSQL、ちょっとWHERE句を削除してみたらどうなると思いますか?」 → 実行 → 「うわ、行数がめっちゃ増えた!」
「JOINをINNERからLEFTに変えると、違う結果になるんですよ」 → 実行 → 「あ!NULLが入ってきた…なるほど!」
こんなふうに、“気づきを引き出す問いかけ”+“変化を見る実験”を組み合わせると、 ただの解説が、一緒に探求する楽しい時間に変わります。
小まとめ:「伝わる説明」は、ちょっとした工夫の積み重ね
- 難しい話は、身近なたとえで“翻訳”してみる
- 書き方の前に“動き方”を伝えると理解が深まる
- 教える側が“問いかけ役”になると、学びが自走し始める
そんな風に考えると、「伝わる力」は“持っているか”ではなく“育てていくもの”なんだと感じられるはずです。
次の章では、実際に「この言い方が刺さった!」という説明例や対話の雰囲気を、ケース別にご紹介します。
教えることがちょっと楽しくなってくるかもしれませんよ!
実際に“初心者に刺さった説明”の具体例あれこれ
どんなに知識を持っていても、 「どう伝えるか」で相手の理解度は大きく変わってきます。
ここでは、実際に私が試してよかった、 そして「それ分かりやすいかも!」と反応が良かった説明のパターンを紹介します。
ケース①:「JOINって、何がくっついてるのか分からない」
初心者のリアクション:
「片方の表にない情報が突然出てきて混乱します」 「どっちのテーブルが先かもよく分からない…」
実際に伝えて刺さった説明:
「JOINって、2つの名簿を照らし合わせて“同じIDの人同士”をくっつける作業だよ。たとえば『生徒名簿』と『テスト結果』をIDで突き合わせる感じ!」
補助として簡単な2行×2行の表を描いて視覚的に補足:
### 📄 生徒名簿(students)
| 学籍番号 | 名前 |
|----------|--------|
| 1 | 太郎 |
| 2 | 花子 |
### 📝 テスト結果(scores)
| 学籍番号 | 点数 |
|----------|------|
| 1 | 85 |目に見える形で「IDが合う=くっつける」がわかると、JOINの意味もスッと入ってくるようでした。
ケース②:「GROUP BYってなんで必要なんですか?」
初心者のリアクション:
「SELECTに書いたカラムをGROUP BYに書かないと怒られるの、理不尽です…」
実際に伝えて刺さった説明:
「GROUP BYは“分類”する命令なんだよ。たとえば売上を『担当者別』に集計するには、まず“担当者ごとの引き出し”に仕分けないと集計できないの」
ここで使ったのが“仕分けボックスの比喩”:
各担当者ごとに箱があって、その中に注文書類をポンポン入れていく → 箱ごとに件数や金額を数える
この「分けてから数える」という視点が伝わると、GROUP BYの存在意義がぐっと納得されやすくなりました!
ケース③:「NULLの扱いで意味不明に…」
初心者のリアクション:
「= NULL じゃ一致しないの、詐欺ですか?」 「NULL = NULL がFALSEになるの、哲学すぎません?」
実際に伝えて刺さった説明:
「NULLは“まだ何も書いてない空欄”だから、答えが“不明”になるんだよ。だから比較しても『同じかどうかもわからん』っていう判定になる」
このとき、例えたのは履歴書:
書類に“誕生日”が空欄だったら、「この人と同じ誕生日ですか?」って質問に“わかりません”ってなるでしょ?
そして「IS NULLは“空欄チェック”の道具なんだよ〜」という説明に置き換えたことで、納得してもらえました。
ケース④:「WHEREとHAVINGの違いがよくわからない」
実際に伝えて刺さった説明:
「WHEREは“データを集める前のふるい”、HAVINGは“グループにしたあとにもう1回ふるい”にかけるイメージ」
2段階のバケツの例で説明しました:
- WHERE:最初に“条件に合うデータだけ”をバケツに入れる
- GROUP BY:バケツの中を仕分け
- HAVING:仕分け後、条件を満たすグループだけ残す
手順を追って処理の意味を言語化するだけで、「あ、なるほど」の反応をもらえました!
小まとめ:「言い換え」と「たとえ」は、最強の翻訳ツール
- 概念だけじゃなく、感覚と言葉の間に橋をかける
- 「空欄」「照合」「仕分け」など、日常語に置き換える勇気
- 難しい単語は“身近な物語”にして届けると、心に残る
「うまい説明って、別に専門的な言葉で話すことじゃないんだな」と気づいた瞬間でした。
次章では、これまで紹介してきた“伝える力”を、どう育てていくのか?
「自分はまだ説明が下手かも…」と感じたときにできる心がけや工夫をまとめていきます。
伝える力もスキルです。育てていけるものなんです。
「説明が下手でごめんね」
「うまく伝えられない自分が恥ずかしい」
そんなふうに落ち込んでしまった経験、きっとこの記事を読んでくださっているあなたにもあるのではないでしょうか。 (私は何度もありました。むしろ今もちょくちょくあります…!)
教えようとして初めて気づけることがある
誰かにSQLを教えるとき、想像以上に「えっ、それって伝わらないんだ!」という壁にぶつかることがあります。
でも、それって実はものすごく貴重な経験なんです。
- 自分はなぜその構文をそう書いたのか?
- この条件式、何を意図しているのか?
──それらを言葉にしようとして初めて、“自分の理解があいまいだったところ”が見えてくる。
教えることで、自分の理解も深くなる。
そう思えるようになると、伝える時間が「おっかなびっくりの時間」から、「学び直せるチャンス」に変わっていきます。
何度失敗しても、説明力は育てられる
最初から上手に説明できる人はいません。
みんな、ちょっとずつ「うまくいかなかった説明」を積み重ねながら、すこしずつ言い換えのバリエーションや“届く言葉”を増やしていきます。
私も、最初はJOINの説明でひたすら迷子になったり、 LEFT JOINとINNER JOINの違いを「なんとなく」で流してしまったことがあります。
でも、そのたびに相手の表情を見て、 「あ、これは伝わってないな」と感じたり、 「あ!その例えわかりやすいかも」と反応が返ってきたり。
そうやって“対話”のなかで育っていくのが、伝える力なんだと思います。
“やさしく伝えたい”という気持ちがあるだけで充分、最初の一歩です
この記事を書いていて改めて思ったのは、 「どうすれば伝わるかな?」と考えている時点で、 すでにあなたは“やさしい説明ができる人のスタートライン”に立っているということです。
- 完璧な知識よりも、「一緒に考えよう」という姿勢
- 難しい言葉よりも、「わかりやすく言い換えてみよう」という勇気
- 正解を押しつけるよりも、「この例えはどう?」と差し出す工夫
そのすべてが、“伝える力”を育てる栄養になるんだなと、私は思っています。
最後に:伝える人も、学び続ける人なんだと思います
SQLの文法は覚えられても、 人に届く説明のしかたは、実践を通じてしか身につかないものです。
だから、もし伝えようとしてうまくいかなかった日があったとしても、 それはあなたが誰かのために、“学ぼうとしていた証拠”。
伝える力は、スキルです。 スキルは、時間とともに、必ず育っていきます。

この記事は、かつて「ちゃんと教えられない自分が情けない…」と、そっと落ち込んでいた私自身への手紙のつもりで書きました。
「分かったつもり」が「全然伝わらなかった」と気づいたときのあの焦り。 無言になってしまった教える時間。 “説明するって、こんなに難しいのか…”と戸惑ったあの瞬間。
でも今では、それすらも“伝える力を育てる種”だったんだなと感じています。 あなたにも、そんな種がきっとあって、この記事がほんの少しでもその芽を後押しできたなら、こんなに嬉しいことはありません。
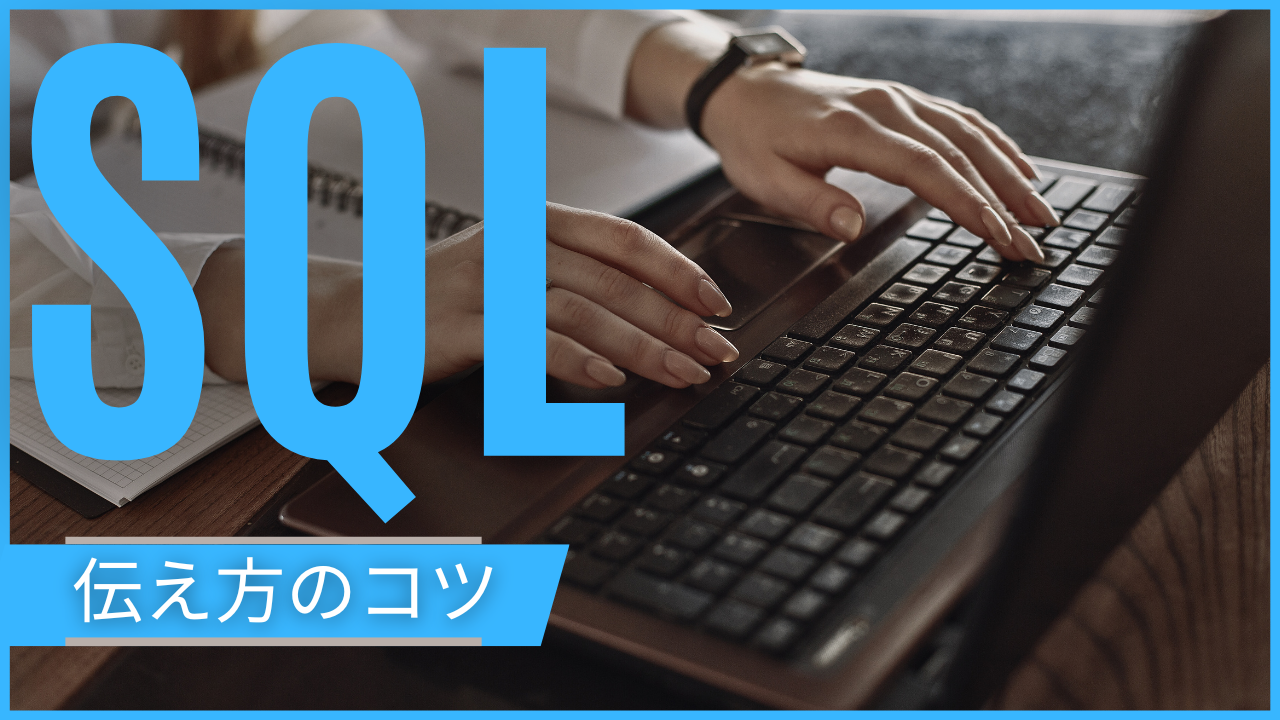
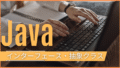

コメント