自分に合う働き方、見つけるまで5年かかりました——
「残業なしの職場が快適か?」 「フレックスなら自由に働ける?」
エンジニアの働き方って、選択肢が多いぶん、迷いやすいと思います。
実際、私自身も“働き方迷子”の時期がありました。
出社必須の現場で毎朝の満員電車に疲弊したり、終業後に謎タスクが降ってくる残業祭りに巻き込まれたり。
「みんなこの環境でどうやって元気に働いてるの!?」って思ってました。
合わない環境って、本当にパフォーマンスを奪うし、心にもじわじわ効いてくるんですよね。
だからこそ、転職や異動をくり返しながら少しずつ整えていった結果、ようやく「自分にとって働きやすい環境はこれかも…!」と思えるところにたどり着きました。
どうやら、私は在宅勤務+ほどよく“静かなチーム”が合っているようです。
この記事では、私自身の経験をもとに、 「どんな働き方が快適なのか?」 「合う環境をどう見つけていったのか?」 をゆるやかに言語化してみました。
働き方にモヤモヤしている誰かに、ヒントが届いたらうれしいです。
「残業なし=快適」じゃない?理想と現実のギャップ
エンジニアとして働き始めてから、いろいろな職場環境を経験してきました。
出社必須・残業多め・リモートなし——これだけ聞くと「うわ…大変そう」と思われるかもしれませんが、実際そのとおりでした。
でも、逆に「残業ゼロ」「フルフレックス」「在宅可」みたいな、“理想的”とされる条件の職場に行ったら快適かと言えば……そうとも限りませんでした。
理想的な働き方ほど、実は「合う・合わない」がある
「定時で帰れる」 「自分で勤務時間を決められる」
これらの条件が嬉しいのは間違いないんですが、問題は—— その働き方が「自分の集中力やリズム」に合っているかどうか。
残業がなくなったのに、なぜか仕事の進みが悪くてストレス。
フレックスになって自由度が上がったのに、時間の使い方がうまくできなくて焦りばかり。
こういうことって、本当にあるんです。
私は「自由な働き方が合ってるはず!」と思い込んでいた時期もありましたが、実際にはその自由に自分が振り回されていたことにも気づかされました。
働き方は“条件”ではなく“設計と相性”の問題
結局のところ、働き方における快適さって「制度の有無」よりも、 その制度が自分の行動パターン・集中力・体調・思考スタイルに合っているかのほうが大事だと思っています。
だからこそ、自分にとっての働きやすさって、一度現場を離れてみないと気づけないこともある。
私自身は、何度か転職や環境変更を経て、少しずつ「これは違うかも」「これは心地いいかも」という手応えを掴んでいきました。
最終的にわかったのは—— 自分に合う働き方は、“制度から与えられるもの”ではなく、“試して体感して気づくもの”だということでした。
次章では、実際に私が経験した「出社必須の現場」「残業多めの職場」で感じた違和感や、そこからどう環境を変えてきたかをお話ししていきます。
過去の働き方を振り返ることで、「どんな環境が合わなかったか?」を言語化していきましょう。
環境に悩んでいた頃の話
「なんか毎日疲れるな…」 エンジニアになって数年が経った頃、私はそんなことをよく思っていました。
仕事が嫌いなわけじゃないし、技術的にも少しずつできることは増えていた。
でも、妙に気が重い。 タスクをこなしても達成感が薄い。
週明けが来るたびに、謎のストレスを感じる。
その原因は“仕事内容”じゃなく“働き方の相性”だった
当時の現場は出社必須、残業もそこそこある環境。
業務自体は面白かったし、メンバーも悪くなかった。
でも、毎朝満員電車で1時間かけて通勤。
夕方には疲労感がピークに達していて、そのあとに残業。
家に帰っても頭が回らない。週末は寝て終わる。
そんな日々を繰り返すうちに、「自分はこの働き方で、最大限の力を発揮できているんだろうか?」と疑問を持つようになりました。
メンタルの調子も微妙で、なんでもないことに対して不安を感じることもありました。
無意識に“他人の理想”に合わせていた
思えばあの頃の私は、 「残業はあるけど、それが普通」 「みんな出社してるし、自分もそうするべき」
そんな風に、“業界の慣習”や“周囲の働き方”を自分にも当てはめようとしていたのかもしれません。
でも、それが少しずつ自分をすり減らしていた。
仕事が嫌いになったわけじゃなく、“働き方”が合っていなかっただけなんです。
この気づきは、転職や現場変更を考えるきっかけになりました。
「自分に合う働き方って何だろう?」 そう問い始めたことで、ようやく“選ぶ側”にまわれた感覚が生まれてきたんです。
“働き方”にも相性がある|試行錯誤の実体験
働き方って、意外と「頭で考える理想」と「実際に体験する現実」が違ったりします。
私も、「リモート勤務が合ってるはず」「フレックスならもっとパフォーマンス出るはず」と思って環境を変えたことがあります。
でも、やってみたら「あれ?うまく集中できない…」とか「かえって時間管理がストレスかも…」という新しい壁にぶつかりました。
集中できる時間帯、実は“午後じゃない説”
フレックス制度が導入された時、「やったー!これで夜型生活ができる」と思ったんです。
ところが午後から始業すると、どうにも頭が働かない。
Slackは既読ばかりだし、チームの会話にも乗り遅れてしまう。
試しに、午前中にタスクを少し進めてみたら——驚くほど集中できて、「あれ、自分って朝方寄りだった…?」と気づくことに。
働き方の自由度があるからこそ、「自分のペース」にちゃんと目を向ける必要があるんだなと思いました。
チームの“話しかけ文化”がストレスのもとに
別の現場では、コミュニケーションがとても活発なチームに参加しました。
Slackの雑談チャンネルが盛り上がり、定期的なオンライン朝会があって、常にだれかが何か話している。
正直、最初は楽しそうだなと思っていたのですが——だんだん情報量の多さと“常に誰かに反応しなきゃ”という空気に疲れてしまいました。
自分は、静かに集中できる時間と、必要なコミュニケーションのメリハリがある環境の方がパフォーマンスを出せるタイプだったみたいです。
トライ&エラーで、ようやく見えた“合う働き方”の輪郭
何度か現場や働き方を変えてみたことで、
- 「朝に頭を使う作業をするほうが向いている」
- 「在宅勤務で自分のペースを保つのが合っている」
- 「必要以上に話しかけられない方が集中しやすい」
という、自分の“快適ライン”が少しずつ見えてきました。
逆に言うと、快適に働くって「環境が良ければOK」ではなく、自分の特性を理解して、それを許してくれる環境との相性を探すことなんですよね。
次章では、“理想の環境を見つける”だけでなく、「今ある環境をどう整えれば、自分らしく働けるのか?」という視点で考えていきます。
制度に頼らず、自分仕様の働き方を作っていくヒントをお届けします。
「快適な働き方」は“条件”ではなく“整え方”だった
「この会社はリモート制度があるから、きっと快適に働ける」
「フレックス勤務できるなら、自由な働き方ができるはず」
……なんて思っていた時期もありました。
でも、いざ入ってみたら思ったより忙しい。自由がある分、自己管理がむずかしい。
Slackが飛び交いまくる。
働きやすさって、制度だけでは成り立たないんですよね。
むしろ、その制度の中でどう働くか?どう整えるか?が、快適さに直結しているなと感じます。
「整える力」も働き方の一部
ここで言う整える力って、具体的にはこんな感じです
- タスクを“午前中に集中して終わらせる”など時間帯のコントロール
- Slackや通知に振り回されず、優先度のある作業を守るルール作り
- 体調や気分によって仕事の重さを調整する意識
これができると、「同じ制度」でも働きやすさがまったく違います。
制度は“土台”でしかなくて、快適さの“中身”は自分で作るんだなって、何度か現場を変えて実感しました。
言語化と小さな仕組みづくりが効く
私の場合、日々の働き方をメモに残すようになってから、何が快適で、何がストレスかが見えてきました。
たとえば
- 午前中に頭を使う作業をするとパフォーマンスが高い
- 昼食後すぐに会議があると、集中力が落ちがち
- 1日に3回以上通知が鳴ると、作業効率が下がる
こういった細かい気づきを、チームとの調整や自分のスケジュール設計に反映していくことで、快適な働き方を自分仕様にしていけるようになりました。
自分で調整できるからこそ、働き方に“選択肢”が生まれる
働き方の快適さって、「どこで働くか」「どんな制度があるか」だけでは測れません。
むしろ、「自分の特性を知って、それに合わせて働けるかどうか」がカギ。
制度の中で自分をすり減らすのではなく、 自分に合う働き方を“整えていける力”そのものが、働き方の質を左右するんだと思います。
次章では、理想の働き方が最初から用意されているわけではないからこそ、「育てていく感覚」が大事だよねという締めの視点につなげていきます。
働き方って“つくるもの”なんだなと感じられるようなメッセージをお届けできたらと思います。
「自分に合う環境」は“見つける”より“育てる”もの
働きやすい環境って、ずっと「どこかにある正解を見つけなきゃ」と思っていました。 残業がない場所、制度が整った会社、自由度の高い現場……
きっと理想の職場はどこかにあって、自分はそこへたどり着く旅をしている。
そんな風に考えていたんです。
でも、いろんな現場や制度を経験するうちに、気づいたことがあります。
働き方の快適さは「完成品」ではなく「素材」。
その素材をどう自分に合う形に整えていくかが大切なんだって。
最初から“完璧な場所”はない
リモート勤務、フレックス、裁量労働……制度は整っていても、文化が合わなかったり、チームの動き方がハイペースすぎたり。
逆に、環境が少し不自由でも、メンバーの関係性や裁量次第で働きやすさはまったく変わったり。
そんなとき、私は気づいたんです
快適さは「与えられる」ものじゃなく、「自分で見つけ、工夫して“育てていく”もの」なんだ。
働き方の正解は、自分で作る
今の私は、在宅勤務というスタイルに落ち着いています。
だけどそれは、最初から“ベスト”と確信していたわけではありません。
- 午前中に頭を使う作業を入れてみる
- Slack通知を減らす工夫をする
- 気が重くなる仕事は「自分ルール」で分割して進めてみる
こんな小さな試行錯誤の積み重ねで、自分仕様の働き方が少しずつ整っていきました。
今では、「働き方って自分で調整できるものなんだ」と思えるようになっています。
まとめ|環境は“育てる”と、ちゃんと応えてくれる
もし今、「働き方がつらい」「この環境は合っていないかも」と思っているなら、 すぐに正解を見つけようとしなくても大丈夫です。
環境を変えるという選択肢もあるけれど、今いる場所にも“整えていける部分”はきっとある。
そしてその積み重ねが、自分らしい働き方につながっていくはずです。
働き方は、“与えられるもの”ではなく、“育てられるもの”。
あなたが自分らしさを大切にすればするほど、環境もそれに応えてくれるかもしれません。

この記事は、自分の働き方にモヤモヤしていた時期の記録でもあり、 少しずつ「自分に合う環境ってこういうことかも」と気づいていく過程のメモでもあります。
働き方の正解って、制度や会社名ではなくて、 “自分のパフォーマンスや心が整う場所”なんじゃないかと、今は思っています。
もし、今の環境がなんとなくしんどいと感じている方がいたら—— 焦らなくて大丈夫。少しずつ整えて、少しずつ育てていけばいいんです。
この記事が、そんな誰かの「自分らしい働き方」を見つけるヒントになったなら、 それ以上にうれしいことはありません。

どんな働き方がいいかって?
うーん…おいしいおやつがあって、静かに集中できる場所が好きだよ。
ぼくの場合ね。

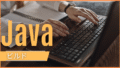

コメント